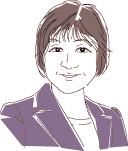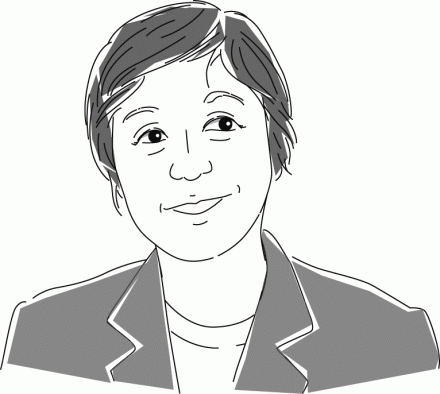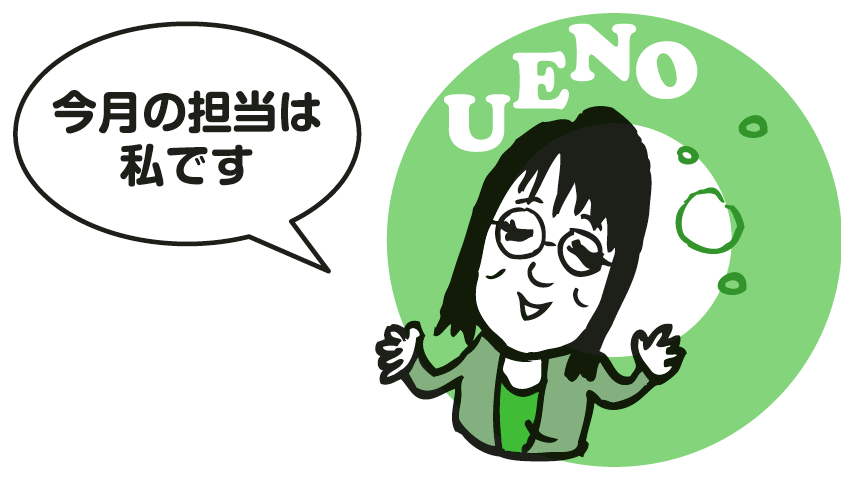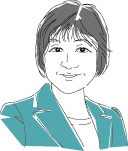本連載では、聖路加国際大学学長の井部俊子さんと、訪問看護パリアン看護部長の川越博美さんが、往復書簡をとおして病院看護と訪問看護のよりよい未来を描きます。さあ、どんな未来が見えてくるのでしょう。
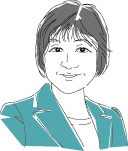
井部俊子さんから川越博美さんへの手紙
診療報酬改定と訪問看護の「評価」
文:井部俊子
2016年の立春も過ぎ、「春は名のみの風の寒さや」と歌う『早春賦』が思い出されます。『コミュニティケア』4月号が読者に届くころは、新人看護師が初めての職場で、“恍惚と不安”の中にいるかもしれません。
看護管理者は、活躍してくれた仲間の退職の申し出に「とても悲しい思い」をすると、前回の手紙に書いていましたね。私も同感です。管理者は毎年、スタッフの退職という“対象喪失”を経験して悔やみます。そして辞めていく看護師に苛立ち、退職を申し出た日から退職の日まで、ツンツンしてしまうという事態が起きることもあります。一方、スタッフからみると、それまで同志のように働いてきた上司が、手のひらを返したような冷たい対応をとることに心を痛めます。新人管理者は、対象喪失からなかなか抜け切れないでいると、抑うつ的になり意欲を失います。管理者はこのような体験を積み重ねて、自己を律して気持ちを切り替えるという修練をするのですよね。私は、そうした中にいる若い管理者には、「それでも『あなたとまた仕事をしたいと思っている』というメッセージを退職するスタッフに伝えなければならない」と言いたいと思います。決して“けんか別れ”をしてはいけないのです。
→続きは本誌で(コミュニティケア2016年4月号)