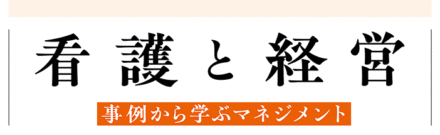●監修 福井 トシ子
国際医療福祉大学大学院副大学院長/教授
●企画協力
鳥海 和輝
『Gem Med』編集主幹
小野田 舞
一般社団法人看護系学会等社会保険連合 事務局長
診療報酬等に関連する用語の理解や管理指標の持つ意味、病院機能ごとの経営の考え方について解説するとともに、事例を通じて、看護管理者が病院経営に貢献するためのヒントを探ります。
*vol.1〜6は【解説編】、vol.7以降は【実践編】となります。
vol.18 実践編⑫
在院日数短縮・入退院支援加算の算定率向上・ 新規患者獲得をめざす
鳥海 和輝
とりうみ・かずき◉大学卒業後、社会保障系出版社に勤務。医療保
険専門誌、介護保険専門誌の記者やデスク等を経て現職。現在、
ニュースサイト『Gem Med』にて、医療政策・行政情報を発信し
ている。
急性期病院の入院が
「要介護度悪化」につながることも
前号で、DPC病院では、入院患者を期間Ⅱまでに退院させることが病院経営にとっても、患者のADL・QOLなどの点からも非常に重要であること、さらに期間Ⅱまでの退院に向けて、後方病院や介護施設などとの連携を進める必要があることを確認しました。今回は、このうちの「急性期病院から回復期病院などへの早期転院」に焦点を当てて、その重要性を考えてみます。
高齢化が進展し、急性期病院でも入院患者の高齢化が進んでいます。厚生労働省の調査によると、7対1看護配置をしている【急性期一般入院料1】病棟でも70歳以上の高齢者が70%近くを占めていることがわかりました。また、2024年度の診療報酬・介護報酬同時改定に向けた中央社会保険医療協議会と社会保障審議会介護給付費分科会の意見交換会では、次のような驚くべき研究結果が報告されています。
・高齢者や認知症患者などでは、「入院による安静臥床を原因とする 歩行障害、下肢・体幹の筋力低下などの機能障害(特に運動障害)」(入院関連機能障害)が比較的起こりやすい
・在宅の要介護高齢者について、要介護度が悪化する要因として、「加齢」に次いで「10対1以上の急性期病棟への入院」が挙げられる(図表1)
・安静臥床によって、筋力低下・骨密度減少・肺炎罹患などが生じやすくなる
・ギプス固定で1日につき1~4%、3~5週間で約50%の筋力低下が生じる
・疾病保有者では10日間の安静で17.7%の筋肉量減少が生じる
・3週間の安静臥床により骨盤の骨密度は7.3%低下する
・長期臥床により呼吸機能の低下が生じ、肺炎に罹患しやすく、治りにくい悪循環に陥る
・高齢者に対する入院中の安静臥床や低活動は、ADLの低下ならびに新規施設入所に関連する