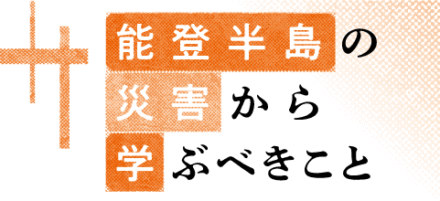
第4回
能登半島地震の災害関連死①
上田 耕蔵◉1975 年神戸大学医学部卒業後、神戸医療生活協同組合神戸協同病院に就職。1993 年より現職。1995 年の阪神・淡路大震災において災害関連死という概念を提唱した。
災害関連死は災害ごとに違う様相を見せます。能登半島地震の特徴は、①後期高齢者比率増:福祉施設支援の課題、②地理的問題:自衛隊空白地、③医療職員不足:災害拠点病院の機能低下です。さらにマスコミの災害関連死の捉え方に問題を感じました。概念の見直しも必要と思われます。
災害関連死数の予測
1.後期高齢化率と災害関連死の推移
阪神・淡路大震災は高齢化社会型震災とされましたが、1995年神戸市の後期高齢化率は5.0%でした。その後、後期高齢化率は上昇を続けます。2011年東日本大震災の岩手県は14.4%、令和6年能登半島地震の輪島市は28.1%に上りました。災害関連死に占める後期高齢者の比率は熊本地震以降では70%前後のようですが、能登半島地震ではさらに高率の可能性があります。平成16年(2004年)新潟県中越地震では52.9%(3次災害の3人を除くと56.1%)でしたが、中規模であったことと、介護保険の弾力的運用で後期高齢者の被害が少なかったためと考えられます。







