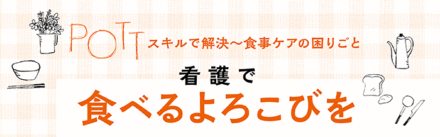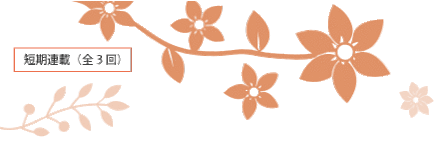鹿児島大学病院看護部、鹿児島県看護協会、NPO法人メッセンジャーナースかごしまの活動等を通じて、離島へき地における看護の課題に取り組む筆者からの報告を2回にわたって紹介します。
田畑 千穂子 ● たばた ちほこ
NPO 法人メッセンジャーナースかごしま 代表
鹿児島県看護連盟 会長
今回は、十島村における看護師2人体制実現の経緯をはじめ、中之島で行った健康教室、口之島での人生会議、そして島民への自宅訪問の様子を通して、離島での看護職の活躍と住民との深いかかわりについて報告します。
十島村における看護師2人体制の実現
2016年、鹿児島大学地域防災教育センター主催の「第4回かごしま国際フォーラム」が開催されました。大会テーマは「島嶼・へき地のルーラルナーシングと災害看護」でした1)。カナダのサスカチュワン大学看護学講師Mary E. Andrews氏が「カナダのへき地における看護実践の課題」を講演し、その質疑応答で十島村の参加者から看護師配置人数について聞かれたAndrews氏は、「カナダでは、看護師の在宅訪問の移動はセスナ機で、看護師は2人体制」だと回答しました。
この「看護師2人体制」の情報を受けた十島村の村長は、すぐさま「十島でも看護師2人体制を導入する」と決断し、予算化が進められました。それから9年がたち、現在では5つの島で2人体制が実現しています。
この国際フォーラムの開催が十島の医療体制に影響を与えたことが成功体験となり、「看護研究活動は社会を変える」「一歩でも前へ動かす行動力が誰かの心を動かし、いつか山が動く」という信念が筆者の看護活動の「芯」となりました。
その後、県看護協会長であった筆者は、十島村の看護師確保のため、eナースセンターへの募集協力や県看護協会の広報誌への記事掲載などを続けました。