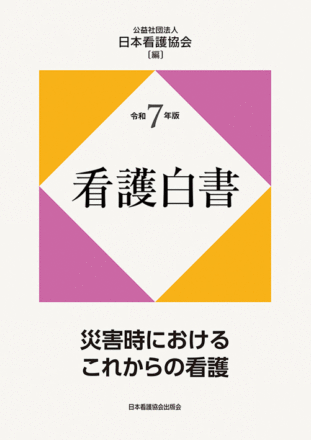自然災害や新興感染症の発生に際し、看護は何をなすべきか
災害支援ナースや医療・保健・福祉活動チーム、
関係団体等の活動事例を交え、具体的に解説!
看護界における〈最新・最重要のデータと情報〉を集約して発信する『看護白書』。令和7年版では、医療法・感染症法改正に伴い、2024年4月より「災害・感染症医療業務従事者」として法制度等に基づく新たな仕組みとなった「災害支援ナース」について解説するとともに、同年に能登地方で発生した災害に対する支援活動を、災害支援ナースや関係機関等の看護職ら自身が振り返り、整理します。
法令等に基づく新たな仕組みとなった
災害支援ナース
1995年1月発生の阪神・淡路大震災において、兵庫県看護協会と兵庫県立看護大学(現・兵庫県立大学)が連携し、看護ボランティアの派遣調整を行ったことが、「災害支援ナース」誕生のきっかけとなりました。
以降、2011年3月発生の東日本大震災や2016年4月発生の熊本地震、2024年1月発生の能登半島地震などの災害時において、多くの災害支援ナースが被災地等に派遣され、救護・支援に尽力してきました。
しかし、災害支援ナースはボランティアであり、被災地等への派遣に当たっては、勤務先の医療機関等で休暇を取得して活動することが多く、事故補償のあり方や活動対価などの課題が存在しました。
さらに、2020年からの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行拡大において看護ニーズの高まりを経験したことで、感染症対策においても看護職の重要性が認識され、これを受けて、医療法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)が改正され、2024年4月より災害支援ナースは、DMAT(災害派遣医療チーム)やDPAT(災害派遣精神医療チーム)と同様、「災害・感染症医療業務従事者」として位置づけられました。これにより、災害支援ナースの派遣に関する費用は公的負担となり、安定的に、かつ、安心して実施できる環境が整備されました。
1章 新たな「災害支援ナース」の仕組みでは、法改正により整備された現在の派遣体制や養成、登録などについて解説します。
令和6年能登半島地震における
災害支援ナースの活動
2024(令和6)年1月1日、石川県の能登地方を震源とする大規模な地震が発生しました。
甚大な被害を受け、現地の医療機関や避難所等において看護支援の必要性が明らかとなったため、石川県は日本看護協会、石川県看護協会に対し、災害支援ナースの派遣を要請。日本看護協会、石川県看護協会の職員も、石川県保健医療福祉調整本部に参集し、石川県と連携して、避難所等への災害支援ナースの派遣調整を行いました。
2章 災害支援ナースの活動では、令和6年能登半島地震における(法改正前当時の仕組みの中での)災害支援ナースの活動を総括するとともに、派遣調整等を担った石川県行政、石川県看護協会、日本看護協会、そして、避難所等で救護・支援に携わった災害支援ナースら自身が、現地での活動を振り返り、今後の課題などを考察します。
災害時における医療・保健・福祉活動チームや
関係団体等の活躍と看護の役割
災害時には、災害支援ナースのほかにもさまざまな医療・保健・福祉活動チームや関係団体、スペシャリストらが、災害急性期の救急医療をはじめ、精神科、周産期領域の医療・保健支援、避難所等での感染症対策、さらに、生活支援や支援者に対する支援、管理体制整備など、それぞれの専門性を発揮しながら、連携・協働して救護・支援に従事します。また、災害時に備え、平時からの訓練や教育のほか、地域での防災・減災の啓発にも取り組んでいます。
3章 災害時における看護の役割では、それら各支援チーム、関係団体やスペシャリストについて、その背景や役割などを紹介しつつ、令和6年能登半島地震における救護・支援活動を振り返り、災害時における看護の役割を考察します。
組織・看護管理者に求められる取り組み
日本では近年、地震や豪雨などの自然災害、感染症といった健康危機が頻発、また、激甚化しています。そうした事態では医療・保健・福祉のニーズが増大し、それらのいずれにも所属する看護職の役割と負担も大きなものとなります。
地域住民、そして、現場でその救助や支援に携わる看護職をはじめとする医療機関等職員の健康と安全を守るには、どのように備えればよいのでしょうか。
4章 今後の自然災害・新興感染症への備えでは、今後の災害対応において押さえておくべき概念や知識、看護管理者らによる自施設での対策などを紹介し、組織や看護管理者に求められる取り組みや心構えなどを考察します。
*
この数年を振り返ってみても、日本は複数回の大規模な自然災害、そしてCOVID-19の感染拡大という非常事態を経験しています。さらに、南海トラフ地震や首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震といった巨大地震が近い将来発生すると言われており、私たちの災害への意識は高まりつつあります。
本書では、主に令和6年能登半島地震の被災地に対して行われた看護活動を例に、さまざまな立場や専門性のもとで災害支援・対策に取り組む看護職について紹介しています。こうした具体的な活動を知ること、理解することによって、災害時における看護職の役割、そして、平時から求められる備えや取り組みについて考える、あるいは見直すきっかけとしていただければ幸いです。
新刊情報
令和7年版看護白書
災害時におけるこれからの看護
公益社団法人日本看護協会 編
●B5判 216ページ
●定価 4,290円
(本体3,900円+税10%)
ISBN978-4-8180-2937-8
発行 日本看護協会出版会
(TEL:0436-23-3271)
Contents
1章 新たな「災害支援ナース」の仕組み(法令等に基づく仕 組みとなった災害支援ナース/災害支援ナースの概要と応援派遣体制/災害支援ナース養成研修)
2章 災害支援ナースの活動(石川県行政の活動/石川県看 護協会の活動/災害支援ナースの活動①急性期の避難所支援活動/同②A避難所での活動と災害支援ナースの今後)
3章 災害時における看護の役割(DMAT/DPAT/DICT/ DHEAT/保健師等チーム/日本赤十字社/日本災害看護学会/災害看護専門看護師/災害時小児周産期リエゾン)
4章 今後の自然災害・新興感染症への備え(オールハザー ドへの対応/支援災害に対する看護管理者の取り組み/新興感染症に対する看護管理者の取り組み)
資料編(看護職の年次データ/看護政策関連の動向/日本看 護協会の主な取り組み)