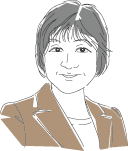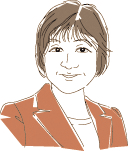福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。
秋の雑感
今年の夏を振り返って
文:上野まり
今年はオリンピック・パラリンピックイヤーでした。気温が高く暑い夏でしたが、早朝にかけて応援でさらに熱くなった人もいたでしょう。4年後の東京オリンピックを視野に入れてか、日本代表選手が準決勝や決勝に進む競技が多く、私も寝不足になるとわかっていてもテレビのスイッチが切れない……という日が続きました。柔道やレスリング、重量挙げ、水泳など、これまでも多くの選手が活躍してきた競技には期待が大きく、金メダルが取れないという贅沢な悔しさを何度も味わいました。