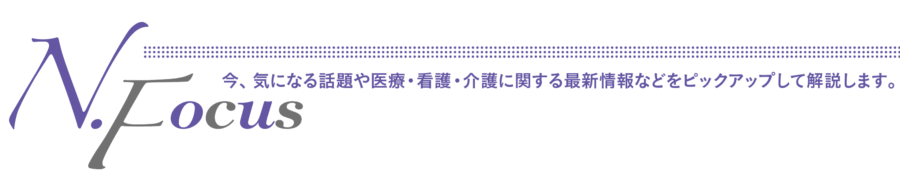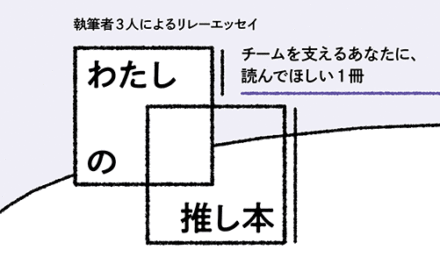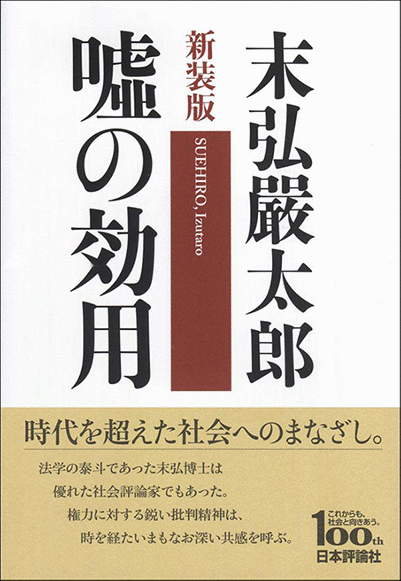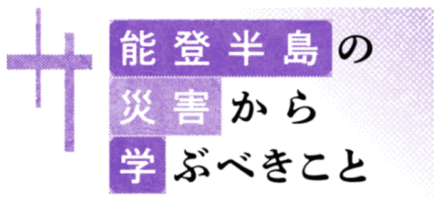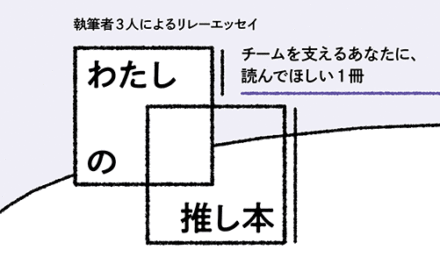
第 1 回『新装版 嘘の効用』
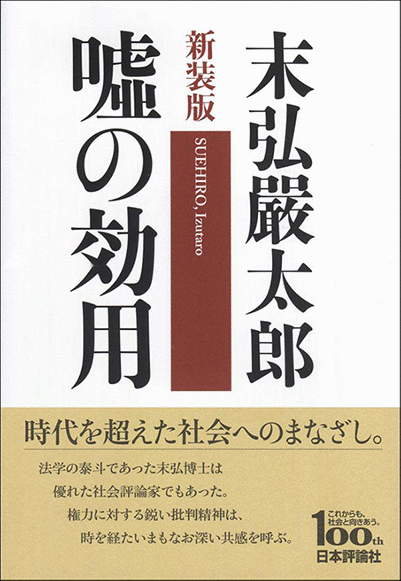 著者:末弘 嚴太郎 価格:2,640円(税込み) 発行:日本評論社
著者:末弘 嚴太郎 価格:2,640円(税込み) 発行:日本評論社
今月の推し人
任 和子
京都大学大学院 医学研究科人間健康科学系専攻 先端中核看護学講座生活習慣病看護学分野 教授
正論の板挟みに遭い、組織の硬直化にため息をついたことのない管理者はいないだろう。私は2011年から京都大学大学院で教授を務めているが、それ以前は京都大学医学部附属病院で副看護部長・看護部長を計6年間経験した。大きな組織のかじ取りを担う中で実感したのは、マニュアルや正論といった定規だけではかりきれない、人と人とが織りなす現場の奥深さと、それを整えることの難しさであった。そうした管理職としての私の長年の葛藤を、静かに言語化してくれたのが本書に収められた随筆「嘘の効用」である。
社会を回す“ゆとり”としての知恵
著者の末弘嚴太郎氏は、大正から昭和にかけて活躍した法学者である。本書で彼は、一般に悪とされる嘘が、実は法律や社会を円滑に動かすための重要な擬制(フィクション)や潤滑油として機能していることをユーモアたっぷりに論じている。
正直は美徳だが、実態に即さない厳格なルールを現場に強いれば、スタッフの自律性は失われ、結果として組織の活力を削ぐ。硬直した法律(ルール)と、変化し続ける複雑な人間社会。その間にあるギャップを埋めるためには、機械の「遊び」に相当する、適度な“ゆとり”が必要なのだ。
本書に出合ったのは、新装版が出版されたころであった★1。管理職時代から抱えていた後ろめたさの正体が解き明かされたように感じた。例えば、スタッフAがBの「言い方のきつさ」に悩み、一方でBはAの「仕事の雑さ」にいら立っているとする。管理者は両者の思いを受け止め、組織としての調和を保つために、対話を重ね、着地点を探る。こうした振る舞いは決して八方美人的な態度ではなく、相反する要素が絡み合う連立方程式を解くような、高度な知的作業なのである。
組織を救う「伸縮する尺度」
末弘氏が説く「規則的に伸縮する尺度」という考え方は、建前に縛られがちな組織を救う示唆に富む。医療現場において、安全を守るマニュアルは不可欠だが、それが現場の状況を無視した守れないルールの押しつけになってはいないだろうか。
末弘氏は「子どもに嘘つきが多いのは、親が頑迷な証拠」と述べている。これは、原因をスタッフ個人の資質に求めるのではなく、組織のルールの「硬さ」に目を向けてみようという、管理者への示唆に富んだ提言である。管理者の役割は、正論を振りかざすことではない。ルールやマニュアルという公平な尺度を持ちつつ、状況に応じて納得感のある“伸縮”をさせていくことだ。管理者が遊びを認め、現実的な解を見いだすその柔軟性が、スタッフが安心して誠実に働ける環境をつくる。
組織の壁に突き当たり、閉塞感を覚えたとき、ぜひこの古くて新しい名著を開いてほしい。そこには、しなやかに組織を導き、管理者をやさしく包んでくれる、自由で温かな知恵が詰まっている。
★1 本書は 1980 年刊『末弘著作集Ⅳ』 を底本とし、新装版として 2018 年に刊行された
→看護2026年3月号掲載