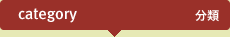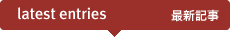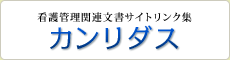〈新連載〉
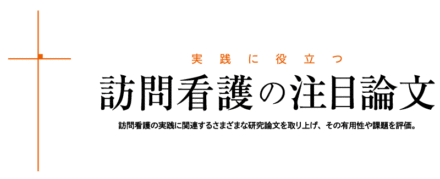
第 11 回
徘徊(ひとり歩き)の人の安全な外出について
山川 みやえ・繁信 和恵・関口 亮子
今月の注目論文
道路網の構造が認知症に関連する行方不明事案に与える影響:
空間的バッファ解析
Puthusseryppady, V., Manley, E., Lowry, E., et al. : Impact of road network structure on dementia-related missing incidents: A spatial buffer approach, Scientific Reports, 10, Article 18574, 2020.
研究者の視点(山川・繁信)
「道に迷う」ことの本当の理由─認知症と環境との関係を理解する視点
認知症の人が一人で外出し、帰れなくなってしまう「徘徊(ひとり歩き)」は、訪問看護の現場でもよく見られます。特にアルツハイマー型認知症では、記憶障害だけでなく、空間認知や見当識の障害がこの問題に影響しています。
アルツハイマー病では、海馬や側頭葉、頭頂葉など空間の把握にかかわる脳の部位が萎縮するため、道順を思い出せなかったり、進む方向を誤ったり、自宅の方向がわからなくなったりします。さらに、見当識障害により「今が何時か」「どこにいるか」「なぜ出かけているのか」といった状況も理解しづらくなります。例えば夕方になって「学校に行かなくては」と言って出ていくなど、本人にとっては自然な行動であっても、現在地や目的地の認識がずれている状態です。
こうした認知機能の低下は、道に迷って帰れなくなるリスクと直結しています。本研究では、行方不明となった認知症の人の周囲には交差点が多く、分かれ道が複雑で、道の方向もばらばらであるという特徴がありました。例えば、四叉路では間違った方向に進む確率が高く、かつ似たような景観が続く場所では誤りに気づきにくくなります。
これは、アルツハイマー型認知症でよく見られる「アロセントリック・ナビゲーション(allocentric navigation)」*1の障害とも関係しています。つまり、頭の中で“地図”を描く力が弱くなっているため、少し道が変わるだけでも方向感覚を失いやすいのです。
訪問看護師として家庭を訪問する際は、このような空間認知の困難さが生活にどう影響しているかに注目してみてください。例えば、「いつものスーパーに行けなくなった」「バス停から家に帰れない」「散歩の途中で遠くまで行ってしまった」といったエピソードがあれば、「認知の地図」が崩れ始めている可能性があります。
支援の工夫としては、次のようなことが考えられます。
①ルートの単純化:交差点が少なく、一本道に近いルートを選ぶ
②目印の活用:電柱番号や看板など、視覚的な手がかりを本人と共有する
③地図での確認:本人と一緒に、家やよく行く場所を線でつなぎ、視覚的に理解を助ける
④外出前の声かけ:家族と一緒に、どこに行くか、どの道を通るかを確認する
また、GPS機器や見守りサービスの利用も有効ですが、本人が拒否したり装着を忘れたりすることもあります。大切なのは迷う前に予防策を講じたり、迷ってしまったときでも大事にならないよう、さまざまな視点で対応できるようにすることです。
今回の研究は、こうした環境要因、特に道路構造が認知症の人の安全な暮らしに大きな影響を与えることを示しました。訪問看護の立場でも、「本人の状態」だけでなく「住んでいる地域の道の構造」に目を向けることで、より実践的な支援が可能になります。
つまり、「徘徊=症状」ではなく、「道に迷う=認知の力と環境とのミスマッチ」と捉えることが大切です。皆さんの観察や声かけが“迷いの芽”に気づくきっかけとなり、行方不明のリスクを防ぐ第一歩になります。利用者が安心して暮らし続けるためにも、環境と行動の両面から支える支援が、今後ますます求められていくでしょう。