ナッジとは、人の心理特性に沿って望ましい行動へと促す設計のこと。ゲストスピーカー・医療職のタマゴたちとともに、看護・介護に役立つヒントを示します。
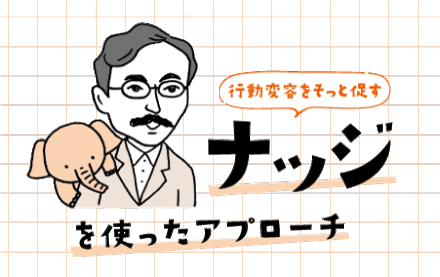
㊲
社会的処方で人生を豊かにするには
竹林 正樹
たけばやし まさき
青森大学 客員教授/行動経済学研究者
三宅 琢
みやけ たく
株式会社Studio Gift Hands 代表
眼科医・産業医/博士(医学)
●●●
医療職のタマゴたちが交代でナッジを学びます。
金田 侑大さん
城戸 初音さん
難波 美羅さん
竹林 今回のゲストスピーカーには、眼科専門医で、LINEヤフー株式会社などの産業医や「社会医」としても活動されている三宅琢先生をお招きしました。三宅先生はStudio Gift Handsという会社を立ち上げ、人と組織のwell-being向上を目的とした教育支援事業も精力的に展開されています。私と三宅先生は一緒に講演を行うこともあり、また、眼科医である私の妻が三宅先生からアドバイスを受けて産業医になった経緯などもあって、公私ともにお世話になっています。
難波 そうなんですね! 社会医というのは初めて聞きましたが、具体的にどういう活動をされるのでしょうか?
三宅 治療に必要な薬の処方だけでなく、人と病気や障害との関係性を変える「社会的処方」を行うことで、well-beingを高めていくのが社会医の役割です。例えば目が不自由な人には、見ることを補助するテクノロジーを処方してできることを増やしたり、社会的孤立を防ぐために同じ病気の人たちと出会える場をつくったりする、そんなイメージです。
難波 公衆衛生と似ているけれど、少し違うようですね。
三宅 対象となる人は重複しますが、目的や評価方法などは異なります。多くの学問が目的にしているのは「専門性を深めること」です。しかし、私は社会医の価値を「広さ」と「越境性」にあると捉え、普通なら医師が取り組まないような領域にも積極的にかかわっています。また、公衆衛生では統計解析による定量評価を重視しますが、社会医としてはむしろ定性評価こそが大切だと考えます。例えば世界中の多くの人に影響を与えた医療関連の映画や漫画などついて、実際にそれらへの感動から生まれた社会全体のインパクトを定量評価することは難しいでしょう。しかし、そのように「いかに人の心を動かしたか」といった定性評価を大切にするのが社会医であると言えます。







