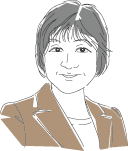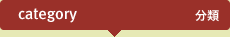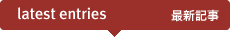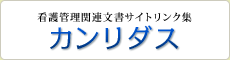本連載では、聖路加国際大学大学院看護学研究科特任教授の井部俊子さんと、訪問看護パリアン看護部長の川越博美さんが、往復書簡をとおして病院看護と訪問看護のよりよい未来を描きます。さあ、どんな未来が見えてくるのでしょう。
井部俊子さんから川越博美さんへの手紙
訪問看護ステーションビジネス
文:井部俊子
“ただ訪問する”ということ
訪問看護をライフワークとしてきたあなたの“昔話”を興味深く拝見しました。
介護保険制度施行以前は、訪問看護師の最大の顧客は医師であり、施行後はケアマネジャーになったという指摘に、訪問看護制度の苦難を
私は感じます。なぜ、顧客は訪問看護サービスを受けたい“住民”にならないのでしょうか。なぜ、訪問看護師は誰かが作成した“訪問看護指示書”や“ケアプラン”に従わなければならないのでしょうか。それらの効能はどのくらいあるのでしょうか。このためにどのくらいの対価が払われているのでしょうか。なぜ、訪問看護師たちはこのような制度矛盾に声を上げないのでしょうか。
こうした“反逆”の延長線上に、あなたが指摘している「人が自分の最期について真剣に考えることが少なくなってきた」ことと、「訪問看護師は、ただ(何も考えずに)訪問していれば済む時代ではなくなった」ことの答えがあるように思います。もっとも、あなたの書簡の正確な記述は「医療が進歩する中で生と死を支えている訪問看護師は、ただ訪問してケアを提供していれば済む時代ではなくなった気がします」です。私が(何も考えずに)と挿入句を入れましたが、このような意味合いで合っていますか。つまり、免疫チェックポイント阻害剤などの開発で延命技術が進み、人は自分の最期を真剣に考えなくなり、「人はいつか必ず死ぬ存在だということを、自分のこととして考えるチャンスがなくなってき」たという箇所です。
私も病院看護師のころ、「とことん(治療を)してほしい」という家族の要請に疑問を持ったことが何度かありました。