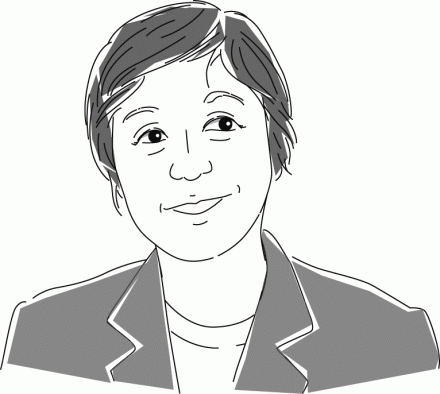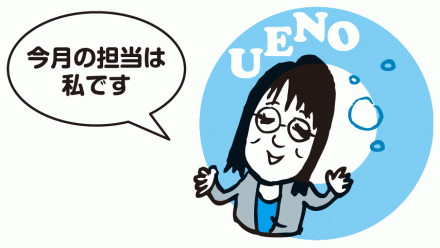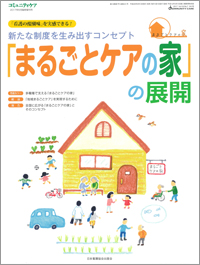 病院を退院した患者は「どこへ」行くのでしょうか? 転院、特別養護老人ホームなどの介護保険サービスの施設、そして自宅が、まず思い浮かぶと思います。しかし、今、地域では新たな“場”への取り組みが始まっています。それが「まるごとケアの家」——そこは制度にとらわれず、どんな人でも受け入れてケアをする場です。患者・家族を看護職・介護職だけでなく、地元の人も加えた緩いつながりで“まるごと”受け入れてケアをする家なのです。
病院を退院した患者は「どこへ」行くのでしょうか? 転院、特別養護老人ホームなどの介護保険サービスの施設、そして自宅が、まず思い浮かぶと思います。しかし、今、地域では新たな“場”への取り組みが始まっています。それが「まるごとケアの家」——そこは制度にとらわれず、どんな人でも受け入れてケアをする場です。患者・家族を看護職・介護職だけでなく、地元の人も加えた緩いつながりで“まるごと”受け入れてケアをする家なのです。
訪問看護師や高齢者施設のナースのための専門誌「コミュニティケア」の2017年6月臨時増刊号では、「まるごとケアの家」について詳しく紹介しています。