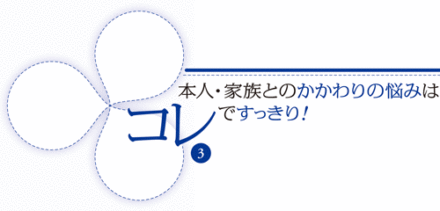怒りの感情と上手に付き合う手法“アンガーマネジメント”を看護職が医療・介護現場で生かすための、基礎知識と看護実践への活用のポイントを解説します。
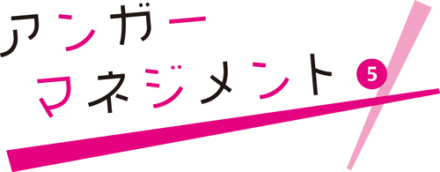
怒りの原因と思考のコントロール
2019年6月号の本連載で、私たちには自分がこうしたい・こうありたい、他者にこうしてほしい・こうあってほしいという期待や欲求があり、感情はこれに伴って生まれると説明しました。
では、怒りはどのように生まれ、私たちはこの感情を抱くとき、何に対して怒りを感じるのか、またその理由はなんでしょうか。
次の例で考えてみましょう。
〈事例〉在宅療養を希望する入院患者Aさんについて、病院で合同カンファレンスを開催することになった。ケアマネジャーのあなたは、病院の退院支援担当者と連携して日程や出席者を調整したが、開催予定日の数日前に、キーパーソンであるAさんの長男から都合がつかなくなったと連絡があった。