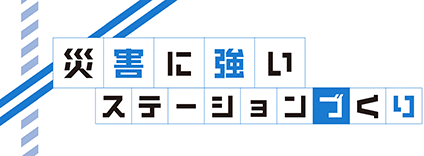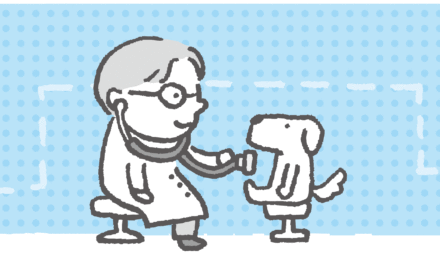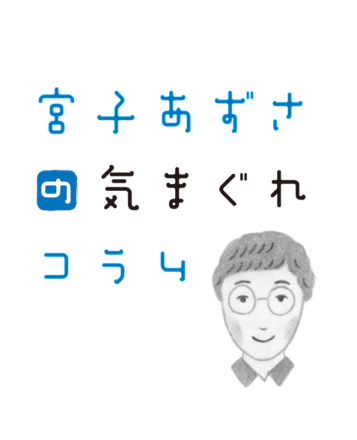訪問看護ステーションや高齢者ケア施設で
生じやすい人事労務に関するトラブルと対応策、
またトラブルの防止策について解説いただきます。
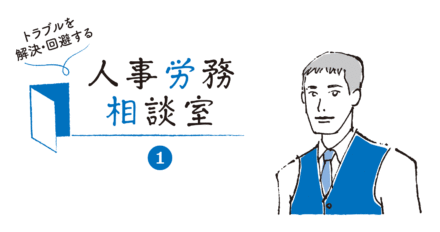
社会保険労務士の活用
中山 伸雄
なかやま のぶお
社会保険労務士法人Nice-One 代表 / 社会保険労務士
「社会保険労務士って、何をしてくれる人ですか?」と、質問を受けることがあります。一方で、すでにお付き合いのある事業所からは、「社会保険労務士って、そんなことまでしてくれるのですか」と、言われることがあります。
このたび、社会保険労務士(以下:社労士)の立場で連載執筆の依頼を受けました。連載開始に当たって、まずは皆さんに社労士の業務について知ってもらおうとの思いに至り、初回となる本稿では、社労士の業務について紹介します。
社労士の主な業務内容
企業の成長には、「金・モノ・人材」が必要と言われています。社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」*1を目的として業務を行っています。業務内容は、事業所における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談対応」など、広範囲にわたります。