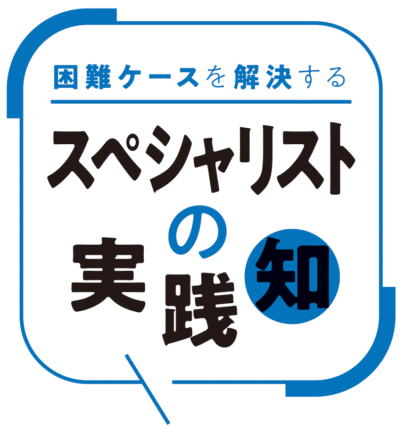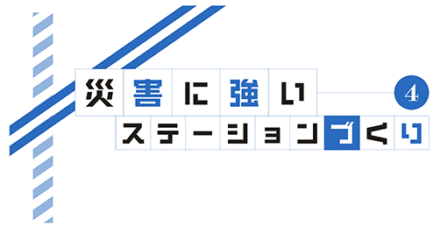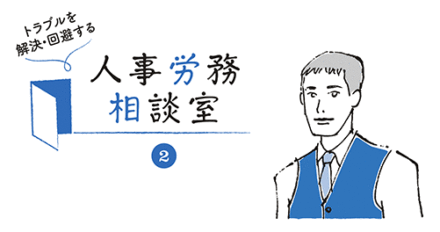各分野のスペシャリストによる看護実践の過程から、困難事例への視点や日々の実践に役立つケア・コミュニケーションのポイント、スキルを学びます。
➓認知症
認知症に対する誤解・偏見に気づき
本人の意思に焦点を当てる
今月のスペシャリスト:田中 和子
突然、大声を出すようになった
脳血管性認知症のAさん
Aさん/80代男性/要介護5
脳梗塞・脳血管性認知症
Aさんは妻と2人暮らし。5年前に右後頭葉脳梗塞を発症して左半身不全麻痺・左半盲となったが、身のまわりのことは自分でできていた。週1回のデイサービスを利用。1年前に左大脳散在性脳梗塞を起こして右半身不全麻痺・運動性失語となり、ほぼ寝たきりの状態となった。以降、排便コントロールの目的で訪問看護が導入された。