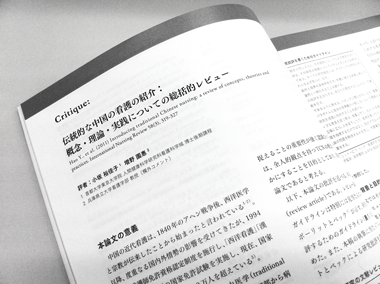“学びながら、つながる”表参道ナースネットが始まります!不定期開催となりますが…新刊書籍を中心とした講演やワークショップ、意見交換や情報共有などを行っていく予定です。著者と、そして参加者同士でつながることができるコミュニケーションの場にぜひ、お気軽にご参加ください!
記念すべき第一回目のテーマは「家族支援をDVDで学ぼう!」です。
①7/14(土)13:00~17:00
「ベッドサイドでの関係づくり――がん終末期患者の家族へのベッドサイドでの支援を例に」
②7/15(日)13:00~17:00
「個人面接での関係づくり――がん終末期患者の家族への退院支援を例に」
〇講師:畠山とも子先生(福島県立医科大学看護学部家族看護学准教授)
児玉久仁子先生(東京慈恵会医科大学附属病院/家族支援CNS)
〇会場:日本看護協会出版会会議室
(東京都渋谷区神宮前5-8-2 日本看護協会ビル4階)

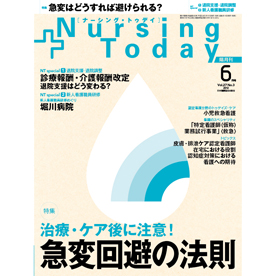 今回は、「治療やケアが終わったあとは、ついついほっとしてしまいがちだけど、それらの処置をしたからこそ起こる急変がある」という考えの下、集中ケア・小児救急・がん化学療法看護の認定看護師の皆様に、それぞれの臨床経験の中から、急変の起こりやすいパターンをお考えいただき、法則としてまとめていただきました。
今回は、「治療やケアが終わったあとは、ついついほっとしてしまいがちだけど、それらの処置をしたからこそ起こる急変がある」という考えの下、集中ケア・小児救急・がん化学療法看護の認定看護師の皆様に、それぞれの臨床経験の中から、急変の起こりやすいパターンをお考えいただき、法則としてまとめていただきました。