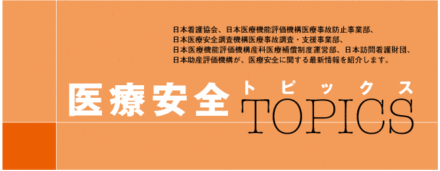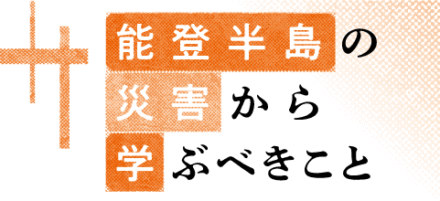各都道府県ナースセンターが病院や施設向けに実施している定着・促進事業の中で得られた「看護職に選ばれる病院・施設」になるためのポイントや、具体例を紹介します!
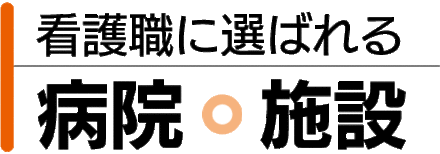
vol.20 秋田県ナースセンターからの提案!
看護職が再就業し
働き続けられる要件とは
成田 睦子
秋田県看護協会
常務理事 兼 秋田県ナースセンター部長
秋田県ナースセンターが実施している再就業促進事業や、求職者への細やかな個別対応などを報告。さらに、再就業者の動向調査から読み取れる選ばれる病院・施設の特徴を説明します。
秋田県の現状
秋田県の人口は、総務省が公表した2024年10月1日時点の人口推計によると89万7千人で、減少率は12年連続で全国1位1)。高齢化率は現在も39.0%と全国1位で、トップを維持したまま2050年には49.9%と人口の約半数が高齢者となり医療需要が高まることが予測されます。
また、秋田県の看護師確保対策事業では病院の需要が減少し、介護保険施設や訪問看護事業所等の需要が増加することが見込まれており、看護職員の在宅医療分野への移行が必要となります。以前から、中小規模の病院・診療所および介護保険施設では、募集人数に対し採用数が確保できない状況でしたが、近年では規模の大きい病院においても看護職員の確保が困難な状況になっています。需要数を供給数が下回る状態は続いており、2029年には実人員で97.7%、常勤換算で95.7%の充足率となる見込みで、人材確保対策は大きな課題となっています。