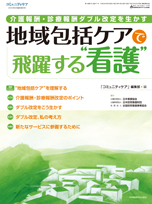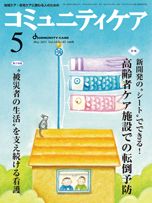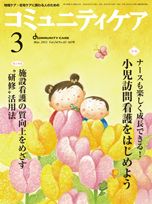コミュニティケア
2012年6月臨時増刊号
介護報酬・診療報酬ダブル改定を生かす
地域包括ケアで飛躍する“看護”
「コミュニティケア」編集部 編
〈協力〉
公益社団法人日本看護協会
公益財団法人日本訪問看護財団
社団法人全国訪問看護事業協会
2012年4月、介護報酬・診療報酬のダブル改定が行われました。今までになく「在宅」「地域」に重点が置かれたものとなっており、訪問看護や施設看護に従事するナースにとって、改定内容を正しく理解し、日常の看護を見直して効率的な事業運営を考えることは必須のことといえましょう。
さらに新たに創設されたサービスにチャレンジすることで、これから間違いなく進む“地域包括ケア”において、まさに“看護”が要となる存在になり、「“看護”を飛躍させる」大きなチャンスを迎えているのです。