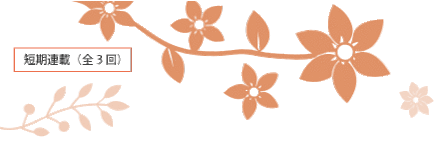
喪失と死を共に受けとめ、助けあって生きる
コンパッション都市・コミュニティへの招待
竹之内 裕文
静岡大学未来社会デザイン機構副機構長
農学部・創造科学技術大学院 教授
第2回:なぜコンパッション都市・コミュニティなのか
今回は、コンパッション都市・コミュニティが求められる理由について、アラン・ケレハーの『コンパッション都市 公衆衛生と終末期ケアの融合』(以下、『コンパッション都市』)に即して、掘り下げて考えます。
予め展望を示しておくことにしましょう。なぜコンパッション都市・コミュニティが必要なのか。それは喪失と死の多様な経験をわかちあい、助けあって生きる社会、つまり喪失と死の多様な経験を包摂する社会を築くためです。これを実現するためには、従来のエンドオブライフケアとパブリックヘルスでは不十分であり、これらを批判的に発展させ、コンパッション都市・コミュニティを築く必要があります。
喪失と死の多様な経験を包摂する
社会を築く
喪失と死の多様な経験をわかちあい、助けあって生きる社会を構想するためには、想像力のはたらきが欠かせません。喪失と死の当事者たちはしばしば、社会の周縁へ置かれ、分断された社会集団を形成し、いわば見えない存在にされているからです。それに応じてケレハーは『コンパッション都市』の冒頭で、ジョン・レノンの『イマジン』を想起させる仕方で、「想像してみよう」(imagine)と読者に呼びかけます。
想像してみよう。コミュニティでは、そのメンバーの健康と社会的ウェルビーイング(良好な生の状態)が気にかけられている。想像してみよう。その気づかいは、コミュニティの一人ひとりが経験する死にゆくこと(dying)、死(death)、喪失(loss)に及んでいる。想像してみよう。ここで「死」の理解は、たんに身体の死にとどまらず、アイデンティティの死や帰属の死を含んでいる。これらの死は、認知症や性的虐待の後遺症とともに生きる人びと、また所有権を奪われた先住民や難民が経験しているものだ。(『コンパッション都市』ⅲ頁)







