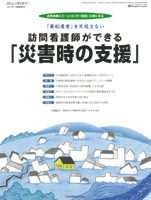 「災害への備えについての本はあるけれど、災害の発生時・発生直後に看護がどうかかわればよいかが書かれたものがあまりない!」と思っていた佐々木裕子さんの企画提案から『「コミュニティケア」2017年11月臨時増刊号・訪問看護師ができる「災害時の支援」』が誕生しました。ここでは佐々木さんに本書のおすすめポイントをうかがいます。
「災害への備えについての本はあるけれど、災害の発生時・発生直後に看護がどうかかわればよいかが書かれたものがあまりない!」と思っていた佐々木裕子さんの企画提案から『「コミュニティケア」2017年11月臨時増刊号・訪問看護師ができる「災害時の支援」』が誕生しました。ここでは佐々木さんに本書のおすすめポイントをうかがいます。
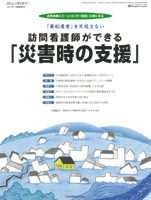 「災害への備えについての本はあるけれど、災害の発生時・発生直後に看護がどうかかわればよいかが書かれたものがあまりない!」と思っていた佐々木裕子さんの企画提案から『「コミュニティケア」2017年11月臨時増刊号・訪問看護師ができる「災害時の支援」』が誕生しました。ここでは佐々木さんに本書のおすすめポイントをうかがいます。
「災害への備えについての本はあるけれど、災害の発生時・発生直後に看護がどうかかわればよいかが書かれたものがあまりない!」と思っていた佐々木裕子さんの企画提案から『「コミュニティケア」2017年11月臨時増刊号・訪問看護師ができる「災害時の支援」』が誕生しました。ここでは佐々木さんに本書のおすすめポイントをうかがいます。
福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。
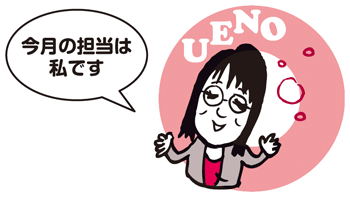
AIが活躍する新たな社会とは
文:上野まり
最近、「AI」(Artificial Intelligence:人工知能)という言葉を頻繁に目や耳にするようになりました。AIの定義はあいまいですが、コンピューターを進化させて人工的につくられた人間と同様の知能のことです。目的を設定すると多大な情報を統合して分析し、その結果に基づいて行動するため、最近ではプロの棋士と将棋の対戦をしたり、車の自動走行に活用したり、時には人間の能力を超える力をさまざまな場で披露し、とても頼もしい存在になりつつあります。
福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。
「食事介助」のあり方を考える
文:鳥海房枝
特別養護老人ホームの入所対象者の介護度が原則要介護3以上になり、入所者の重度化がよりいっそう進んでいます。それに伴って職員には、細心の注意を払った食事介助が求められるようになりました。かつて、食事摂取量が低下したり、誤嚥性肺炎を繰り返したりする入所者に対し、主治医が「経口摂取はリスクがあるが、餓死させるわけにはいかない」と、経鼻経管栄養の導入や胃瘻の増設等、いわゆるチューブでの栄養注入を指示することは珍しくありませんでした。今日ではこのような医師は少なくなったように感じます。その一方で、どのように経口摂取を継続していくかが大きな課題になっています。
福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。
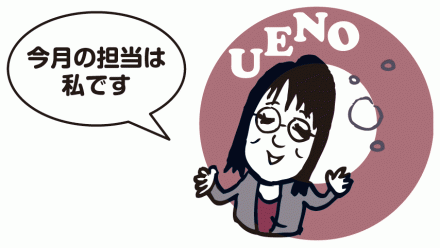
散歩の効能
文:上野まり
いきなり私事で恐縮ですが、雨の日以外は大学まで徒歩で通勤しています。大学は自宅の最寄り駅の反対側にあり、自宅も大学も丘の上にあるため、坂道を下ったり上ったりするルートです。そのおかげか、平日は1日1万歩ほど歩いています。初めのうちは周囲に「それはよい運動ね! さぞかし痩せるでしょう」と言われていましたが、1年半がたち「どうして痩せないの? タラタラ歩いているんじゃない?」と厳しい指摘を受けています。
感性を磨く時間
今の大学に勤務するまでの約20年間は、バスと電車で片道1、2時間かけて通勤していました。電車に乗り遅れないよう走り、押し合いへし合い状態の車両に揺られ、勤務先に着くだけで疲れ果てていました。
看護プロセスや実践知が明示・共有されづらいとされる訪問看護。その業務を“見える化”し、よりよいケアの提供や、管理者・スタッフの仕事の楽しさ向上につなげる方法を、谷口由紀子さんと、山本則子さんを中心とするグループが解説します。
事例研究:看護実践を書き出してキャッチコピーをつくる
池田 真理 ◆山本 則子
前号では、事例研究は看護実践を可視化するのに最適な方法であると提案しました。本号では、事例研究のファースト・ステップとして、看護実践を記述するための具体的な方法を紹介します。
事例研究で取り上げる看護実践の選択
事例研究をするに当たっては、まず事例が必要です。あなたはどのような事例を選ぶでしょうか。「何か印象に残っている事例を書いてください」と言われると、多くの看護職はうまくいかなくて後悔が残った事例や、何かやり残したような感情が伴う事例を挙げます。看護職はいつも、患者がもっと満足するケアを提供したい、自分にはそれができただろうかと考える傾向があり、患者のウェルビーイングを高める看護をしたいという熱意の表れから、自らの反省すべき点に意識が向きがちなのかもしれません。