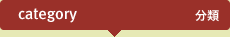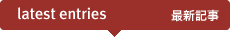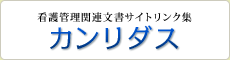福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。
「食事介助」のあり方を考える
文:鳥海房枝
特別養護老人ホームの入所対象者の介護度が原則要介護3以上になり、入所者の重度化がよりいっそう進んでいます。それに伴って職員には、細心の注意を払った食事介助が求められるようになりました。かつて、食事摂取量が低下したり、誤嚥性肺炎を繰り返したりする入所者に対し、主治医が「経口摂取はリスクがあるが、餓死させるわけにはいかない」と、経鼻経管栄養の導入や胃瘻の増設等、いわゆるチューブでの栄養注入を指示することは珍しくありませんでした。今日ではこのような医師は少なくなったように感じます。その一方で、どのように経口摂取を継続していくかが大きな課題になっています。
平成18年度介護報酬改定で栄養マネジメント加算の新設や経口移行加算の見直しがされました。それまで、一部の介護現場では“チューブ外し学会”を標榜して経口摂取への取り組みを発表するなどの動きがありました。これらの背景から、チューブ外しが経口移行加算として認められたのは、極めて画期的な出来事でした。
低栄養の予防と生老病死の折り合い
高齢者ケア施設の職員が食事介助で悩むのは、入所者がいつまで食べられるのか、あるいは食べさせてよいのかということです。「高齢者ケア施設で生活する入所者にとって、食事は楽しみの1つ」とよく言われます。自らの意思で、好きな物を、好きなときに、好きな量だけ食べるのであれば、その考え方は理解できます。しかし入所者は、栄養計算された食事を最期まで提供され続ける受け身の存在です。ある特養では、食事摂取量の低下した入所者の嗜好に合わせた献立を介護職が提案したところ、摂取カロリーが不足するという理由で栄養士の同意が得られなかったというエピソードを最近耳にしました。