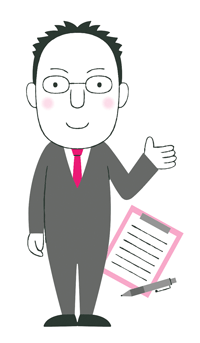訪問看護ステーションの管理者が地域のニーズを的確に捉えて健全
な経営を行い、その理念を実現するために行うべきことを、公認会
計士・税理士・看護師の資格を持つ筆者が解説します。
1時間でできるエリアマーケティング(前編)
渡邉 尚之
皆さんは、自分の訪問看護ステーションがある地域についてエリアマーケティング(商圏分析)をしたことはありますか? これは特別に難しい調査などではなく、簡単に言えば、自ステーションのある地域の特徴や人口動態、医療機関・介護事業所の開設状況、同じ地域で展開しているほかの訪問看護ステーション数や特徴を“見える化”したことがあるか、という意味です。
これらについて専門の調査会社などに依頼すると、非常に細かく調べてくれます。一方で、調査費用が高額であったり、調査の専門家であっても医療・介護についての知識・理解が不十分だったりと、なかなか積極的な活用が難しいという問題があります。
しかし、実はエリアマーケティングは、公表されている官公庁の統計資料や業界団体のデータなどを活用して、自力でもある程度、行うことが可能です。こうした方法であれば、短時間かつコストをかけずに地域の傾向や動向をつかむことができ、効率的です。
そこで、今回・次回の2回にわたり、「1時間でできるエリアマーケティング」の方法を紹介します。

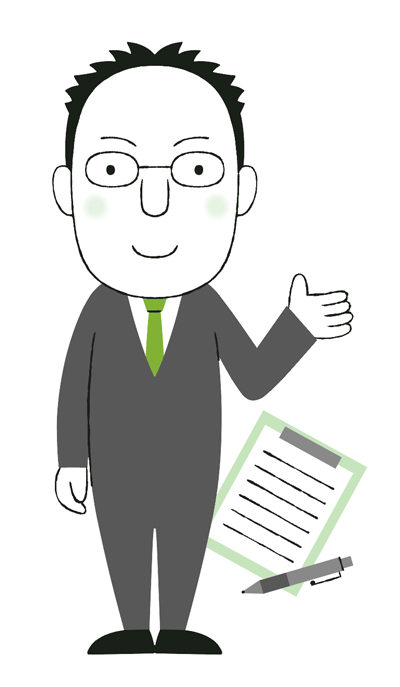
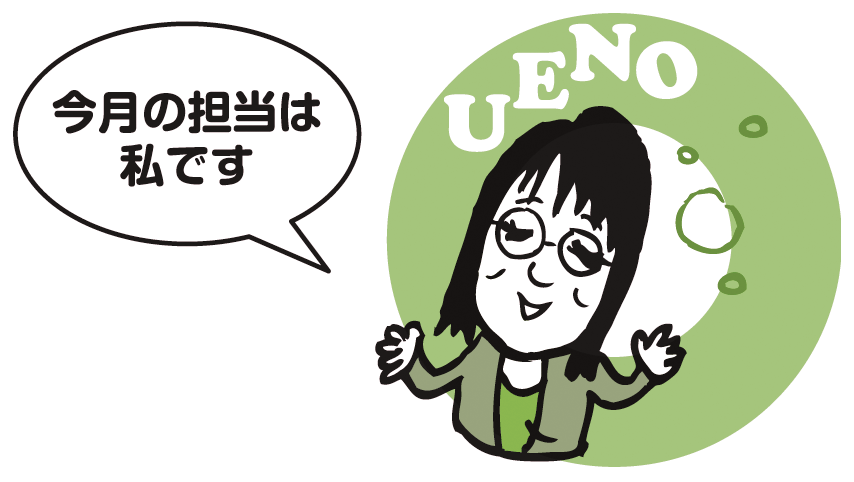
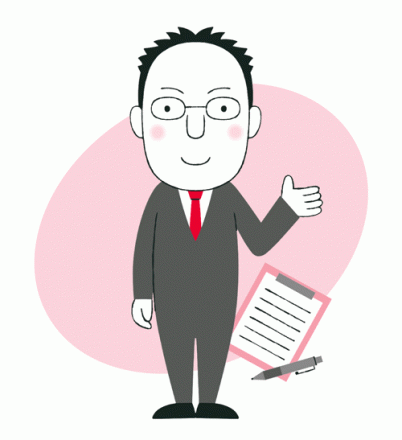 全国の訪問看護ステーション数(稼動数)は、2017年4月1日現在で9735件です。1年間の新規開設数は1234件であるものの、廃止・休止数は686件にも上っています。この数字からも、訪問看護ステーションの経営が決して楽ではないことが推察いただけるのではないでしょうか。
全国の訪問看護ステーション数(稼動数)は、2017年4月1日現在で9735件です。1年間の新規開設数は1234件であるものの、廃止・休止数は686件にも上っています。この数字からも、訪問看護ステーションの経営が決して楽ではないことが推察いただけるのではないでしょうか。