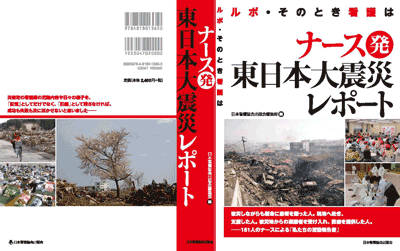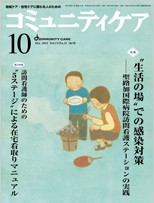『DVDBOOK 臨床での家族支援1 ベッドサイドでの関係づくり』と『DVDBOOK 臨床での家族支援2 個人面接での関係づくり』を同時に刊行しました。


わかっているつもりでも実践が難しい家族看護……。患者・家族への対応力をつけるには「実践のトレーニング」が必要です!DVDで家族への対応の「失敗編」と「成功編」を見ながら、ベッドサイドと個人面接での関係づくりを学びましょう!
〇本書の使い方
附属DVDには同じ事例で異なる対応場面「失敗編」と「成功編」が収録されています。各場面には「解説なし」と「解説入り」の映像があります。DVDを見ながら書籍の解説を読むことで、看護師の振る舞いが患者・家族に与える影響を観察することができます。
ここでは『DVDBOOK臨床での家族支援1 ベッドサイドでの関係づくり』の中でご紹介している【失敗編】場面1:気まずくなってしまう看護師(解説なし/解説入り)を例に、本書の使い方を見てみましょう。