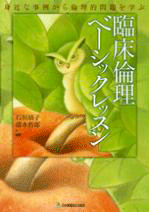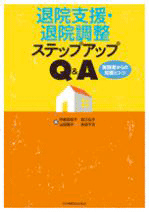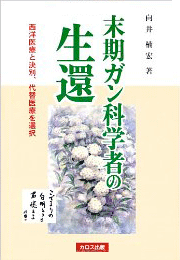
評者:秋田 正雄(元日本看護協会出版会副社長)
この書は「余命3カ月の末期がん」と宣告された科学者(著者)がそれまで受けてきた西洋医療とは大胆にも決別し、代替医療に専念することによって生還を果たしたという、がん闘病実録である。
ある医大病院で手遅れの「神経内分泌細胞がん」と診断されたのが2006年の夏。5年半経過した今、著者は嘘のように回復して元気溌剌の生活を送っている。いったい、あの告知は何だったのだろうか。当時のセカンドオピニオンもほぼ同じ判断をしており、誤診ではなかったはず。西洋医学では説明のつかない不思議な事例であった。