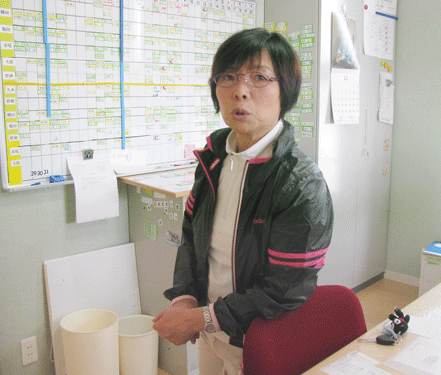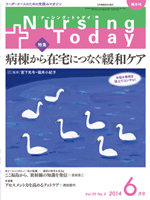〈コミュニティケア探訪・No.30〉
【精神疾患を伴う人への柔軟ケア
利用者との“やったー感”が楽しくて
〜滋賀県湖北の「訪問看護ステーションれもん」
――久木ひろ美さん その2】
■久木ひろ美さん(訪問看護ステーションれもん所長)
看護短期大学を卒業し、近江学園(児童福祉施設)で勤務した後、結婚を機に豊郷病院へと転職。外来を経験した後、訪問看護ステーションレインボウ3カ所を次々に開設する。2012年、定年を前に退職し、訪問看護ステーションの少なかった滋賀県湖北地方で開業。2013年には米原にサテライトを開いた。これからは、暮らしを支える訪問看護の技を、後輩に伝えていきたい。
民生委員をしていた父のところには、悩みを抱える人がいつも話しに来ていた。その父の姿が自分のルーツと思う。
文と写真・村上 紀美子(医療ジャーナリスト)
身近な高齢者トリオが落ち着き、私は仕事に励んでいます。私が編者となった『患者の目線―医療関係者が患者・家族になってわかったこと』(医学書院)は、20人の貴重な体験談が満載でおススメです。
❍
認知症やうつ病など精神疾患を伴う訪問看護の利用者さんは大勢います。どのようなケアが効果的なのでしょうか。滋賀県の「訪問看護ステーションれもん」の久木ひろ美さんたちは、精神科訪問看護の経験も豊かです。その柔軟なケアを、前回(2014年3月号)に続き探訪します。
❍
20年前に初めて訪問看護ステーションを立ち上げたときから、久木さんは精神科訪問看護にずっと携わってきました。久木さんは、もともと精神医療に定評のある豊郷病院で外来師長として患者さんにかかわってきたので、そのころすでに「これからは地域でメンタルヘルスの支援が絶対に必要になる」と見込んでいたのです。
精神科訪問看護についての久木さんの考え方を紹介します。 続きを読む…