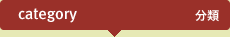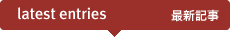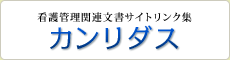評価指標を全国初公開!
“DiNQL(ディンクル)”を詳しく解説した
これからの病棟マネジメントで必読の総特集です
◆総特集
ベンチマーク評価で“看護”を変える!
労働と看護の質向上のためのデータベース事業
DiNQL ディンクル
2012年度よりスタートした日本看護協会の「労働と看護の質向上のためのデータベース事業」(事業愛称:DiNQL ディンクル)。
この事業は病棟看護師長をはじめ、日々、頑張っている看護管理者を応援する事業です。
主に“病棟”単位でデータ比較を行い、ベンチマーク評価を通じた看護管理者の病棟マネジメントをサポートします。
看護実践の内容等を“評価指標”としてITシステムに入力すると、レーダーチャートや推移グラフで“看護の質”が見えて、客観的なデータを基に同規模の病院や他病棟との比較評価が可能になります。
看護実践をデータ化し、全国の病院等から評価指標を収集したデータベースを構築することでベンチマーク評価ができるようになり、日本中の看護職の労働条件・労働環境改善や看護の質向上につなげていくことが期待されます。
2014年度の事業開始に先立ち、「看護」6月臨時増刊号では同事業の概要や2013年度試行事業に参加した病院の声を紹介し、日々の看護をよりよいものにしていくデータマネジメントを考えます。
自分たちの“頑張り”を可視化し、スタッフのモチベーションを向上する手段としても、ご注目ください。
事業キャラクター「ディンキー」の表紙が目印です!