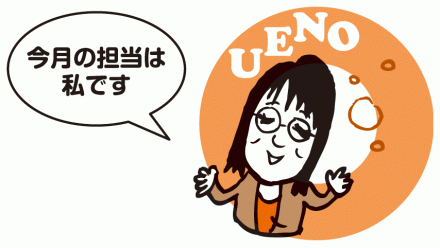福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。

介護現場における
ヒヤリハット報告をめぐって
文:鳥海房枝
介護事故を減らすことを目的に、多くの介護現場でヒヤリハット報告書の提出が奨励されています。その根拠とされているのが、1:29:300のハインリッヒの法則です。これは重大な事故1件の背景には、軽微な事故が29件あり、さらにその背景には事故寸前の案件が300件あるという、米国の損害保険会社の社員・ハインリッヒが提唱した労働災害における経験則です。これを基に「ヒヤリ」としたら、あるいは「ハッ」としたら報告書を作成することで軽微な事故や事故寸前の案件に目を向け、重大な事故の発生を予防しようとする考え方です。