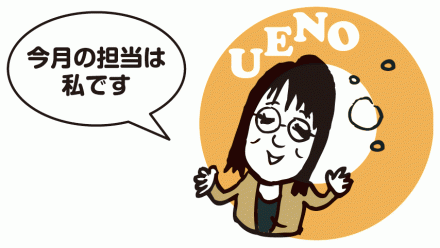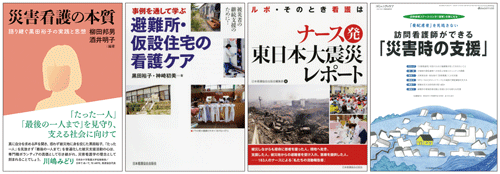訪問看護ステーションの管理者が地域のニーズを的確に捉えて健全
な経営を行い、その理念を実現するために行うべきことを、公認会
計士・税理士・看護師の資格を持つ筆者が解説します。
給与の正しい知識を
身につけよう(後編)
渡邉 尚之
給与等と資金繰り
訪問看護ステーションの経営に不可欠な給与についての知識の後編として、今回は資金繰りに関する留意点を解説します。
訪問看護ステーションを経営する上で、最も大きな支出は看護職をはじめとするスタッフに支給する給与等(給与・賞与)です。給与等の仕組みや支出のタイミングを正しく理解していなければ、給与等に関する多額の支払いが必要となる月などに必要な資金を用意できず、資金不足に陥る危険があります。
そこで、本稿では給与等の基本的な仕組みと留意点、事業主の負担を確認するとともに、モデルケースを用いてそれらの支払いのスケジュール・金額を示します。