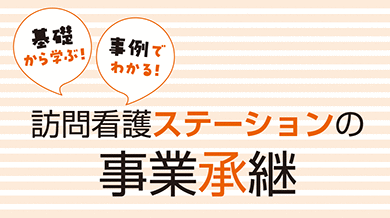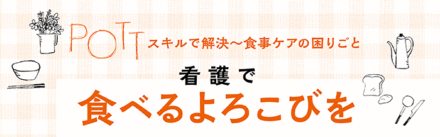経営者の高齢化等により注目されている事業承継。成功させるにはいくつかのポイントがあります。本連載では、事業承継とは何か、事業承継の流れ・留意点などの基礎知識を解説し、実際の支援事例を紹介します。
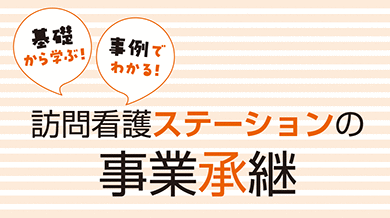
事業承継・引継ぎ支援センター」と
「よろず支援拠点」
坪田 康佑
つぼた こうすけ
訪問看護ステーション事業承継検討委員会
一般社団法人医療振興会代表理事
看護師/国会議員政策担当秘書
事業承継のご相談はお早めに
訪問看護ステーションの経営者は、事業を始めた段階から「いつかは自分も誰かに引き継ぐのだ」という意識を持ち、日常的に準備を進めておくことが非常に重要です。しかし実際には、「自分はまだ元気だし、経営も順調だから」と、事業承継について考えることに抵抗を感じる経営者も少なくありません。
また、中小企業庁の「2023年版 中小企業白書」1)によると、後継者へのバトンタッチに向けた準備には少なくとも1年以上を要したケースが半数以上でした。本格的な承継に向けた組織体制の調整・整備などにかかる手間を考慮すれば、より長い期間が必要になることも珍しくないため、すでに事業承継を考え始めている人も、できるだけ早くから準備をしておく必要があります。
3月号では、経済産業省による事業承継の支援施策である「事業承継・引継ぎ支援センター」(以下、支援センター)2)を紹介しました。全国47都道府県に設置されており、いざというときに頼れる公的な支援機関ですが、実際にはどう活用すればよいのかがわからず、利用に踏み出せない訪問看護事業者も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そのような経営者が将来の事業承継に向けて一歩踏み出せるように、支援センターについてあらためて説明し、その母体である経営相談の窓口「よろず支援拠点」の活用方法も併せて紹介します。
「事業承継・引継ぎ支援センター」の活用
❶多様な売却対象でのサポート
支援センターは、2011年に経済産業省が全国に設置した「事業引継ぎ支援センター」と、2014年度にスタートした「後継者人材バンク事業」を合併して設立しました。第三者への売却だけでなく、親族や社内の役員・従業員への承継、M&A(事業の売買)に関することまで幅広い相談に対応します。また、M&Aアドバイザーや仲介会社の場合は第三者への事業承継を中心とした相談を対象としていますが、支援センターでは、事業主が引退を考える場合のあらゆるケースをサポートします。
例えば、親族内での承継では「事業承継計画」の策定支援が受けられるほか、税務面の相談も可能です。社内での承継を進めたい場合には、後継者となる役員や従業員側へのアドバイスやフォローも丁寧に行ってくれます。また、M&Aを視野に入れている事業主であれば、買い手の探し方やさまざまな手続きについてもしっかりとサポートするなど、多様なニーズに柔軟に対応しています。
そのほかに、訪問看護事業ならではの悩みとして利用者との関係やスタッフの雇用の問題など、引き継ぎに伴うデリケートな問題が挙げられるでしょう。こうした課題についても、プロの視点でアドバイスを受けることができます。
→続きは本誌で(コミュニティケア2025年5月号)