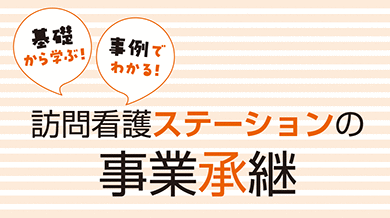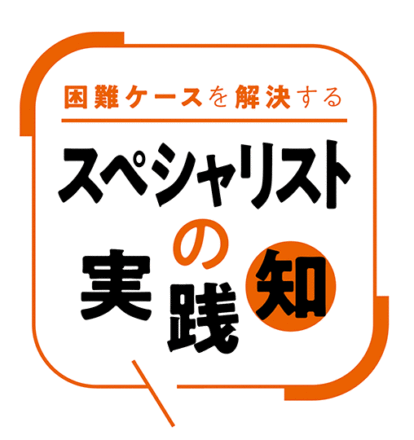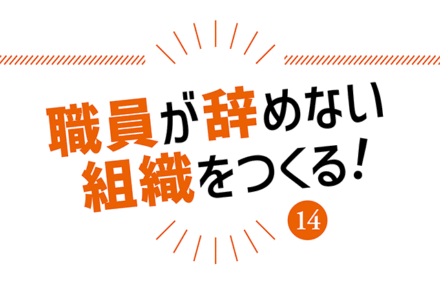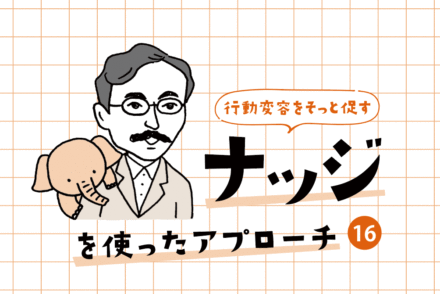経営者の高齢化等により注目されている事業承継。成功させるにはいくつかのポイントがあります。本連載では、事業承継とは何か、事業承継の流れ・留意点などの基礎知識を解説し、実際の支援事例を紹介します。
事業承継は、経営承継と資産承継
坪田 康佑
つぼた こうすけ
訪問看護ステーション事業承継検討委員会
一般社団法人医療振興会 代表理事
看護師/国会議員政策担当秘書
本連載では、訪問看護管理者および経営者に訪問看護事業の事業承継を知ってもらうために、マクロデータやガイドライン1)、事例などを基に、事業承継について多様な視点から解説しています。
前々号・前号では2回にわたって、事業承継の全体像を5つのステップに分けて紹介しました。全体像を把握しておくと、日常業務の延長でできる準備や、めざす経営状況などがわかるため、業務の重複や無駄を減らし、効率的に事業承継に取り組めるようになります。
今回は、事業承継の2つのカテゴリーである「経営の引き継ぎ」と「資産の引き継ぎ」について解説します。