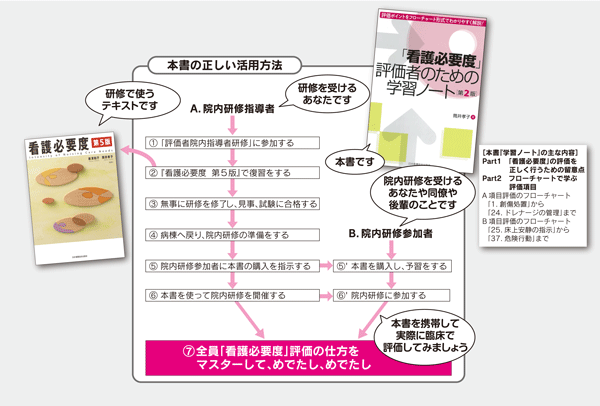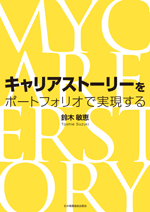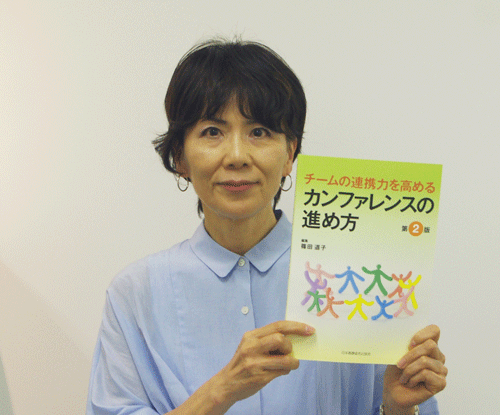
篠田 道子さん(しのだ・みちこ)
日本福祉大学社会福祉学部 教授
看護師免許取得後、筑波大学大学院教育研究科
リハビリテーションコース修了。筑波大学附属病院、
東京都養育院、シルバーサービス会社勤務を経て1999年に日本福祉大学赴任、2008年より現職。2011〜2012年、慶應義塾大学大学院経営管理研究科訪問教授。

地域包括ケアシステムが推進される中、患者・家族を含めた多職種・他機関が参加するカンファレンスが連携・協働の重要なツールとなっています。豊かなカンファレンスを運営するための基本技法を丁寧に解説した『チームの連携力を高めるカンファレンスの進め方 第2版』の編著者・篠田道子さんに、改訂のポイントなどをうかがいました。



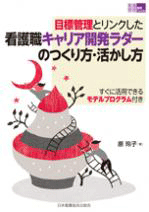 キャリア開発ラダーの構築は、「導入の目的」と「育成したいナース像」を明確にするところから始まります。新刊
キャリア開発ラダーの構築は、「導入の目的」と「育成したいナース像」を明確にするところから始まります。新刊