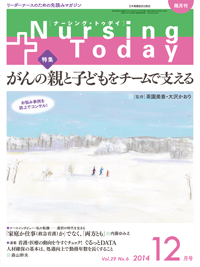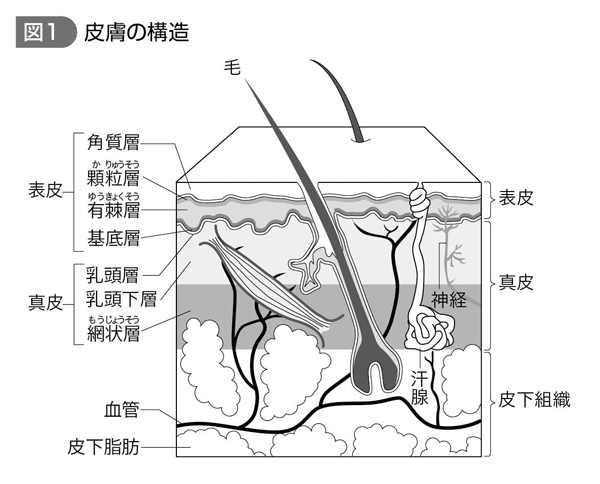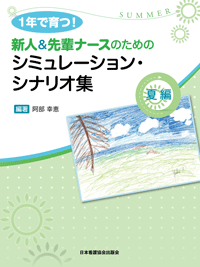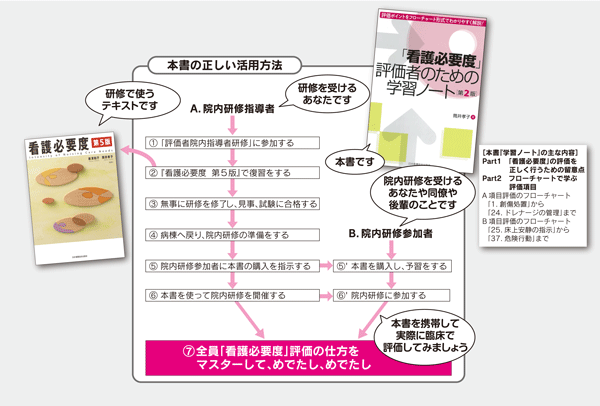【チームづくりのお悩み相談】の
お悩みは、
「新人の技術評価について
指導者同士の見方がさまざまで、
モメています」です。
事例 ▶ 新人看護師の技術評価の際、新人と指導者にギャップがあり、感情的になった指導者が「あなたは看護師に向いていない」と新人に言葉をぶつけています。異なる評価をする指導者もいてチーム内でモメており、どうしたものやら…
評価は測定とは異なり、バラつきが出るのは当たり前です。とはいえ、そのことで職場にはさまざまな波紋が広がります。「技術評価のスキルを磨く」との研修の際に、評価に関する悩みを洗い出し構造化すると、2つの問題「管理(PDCA)サイクルとして動いていない」「評価スキルが不十分である」が見えてきました。
評価はPDCAサイクルを意識して行う
PDCAサイクルは管理の基本サイクルですね(「Plan〔計画〕」「Do〔実行〕」「Check〔評価〕」「Action/Act〔処置・改善〕」の頭文字の略称)。
現在の新人看護職員の評価の実態は、評価リストの同一項目を1年間、数カ月ごとに「1人でできる」「支援の下にできる」「できない」と進めていることが多いようです。ここで一度、次のことを再確認しましょう。
①何のための評価か
②何を評価するのか
③評価を誰にフィードバックするのか
新人に限らず、一般的に人事考課などの目的は、PDCAサイクルの「C (Check)」の段階、つまり「評価」です。まずは、表1の「能力評価の3つの視点」を職場全体で再認識したいものです。新人に「看護師に向いていない」との言葉をぶつけることは、看護部長に「採用のミスではないか」と訴えるつもりでしょうか? まさに「感情が高ぶって論理の飛躍が起きてしまった」ということですね。
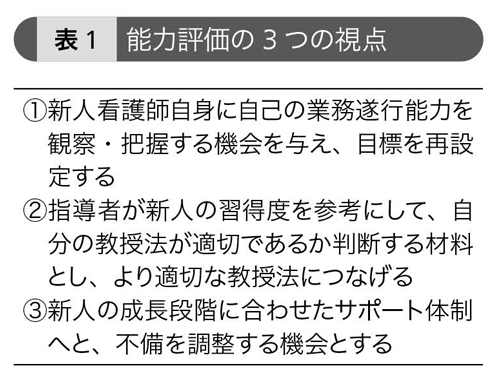
(この続きは本誌で)
[著者]永井 則子(有限会社ビジネスブレーン代表取締役)
NT12月号のその他の内容はこちらから