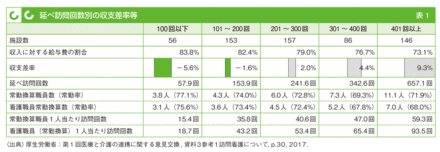怒りの感情と上手に付き合う手法“アンガーマネジメント”を看護職が医療・介護現場で生かすための、基礎知識と看護実践への活用のポイントを解説します。
思考のコントロールと“3つの努力”
光前 麻由美
許容範囲を拡大・明確化する
先月号(「コミュニティケア」2019年8月号)では、三重丸(図1)を用いて“「べき」の境界線”について考えました。
 アンガーマネジメントは怒りで後悔しないことをめざします。自分が何は許せて、何は許せないのかを三重丸に沿って考え、怒るべきことと怒らないことを区別できるようになったら、さらに次の3つの努力をしてみましょう。
アンガーマネジメントは怒りで後悔しないことをめざします。自分が何は許せて、何は許せないのかを三重丸に沿って考え、怒るべきことと怒らないことを区別できるようになったら、さらに次の3つの努力をしてみましょう。
❶ ②を広げる
❷ ②と③の境界線を安定させる
❸ ②と③の境界線を他人に見せる