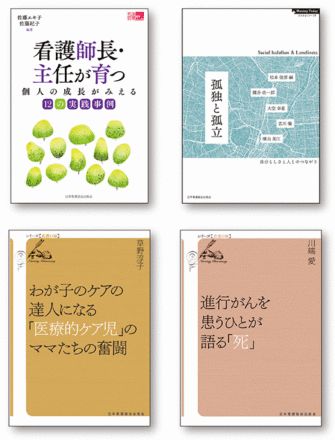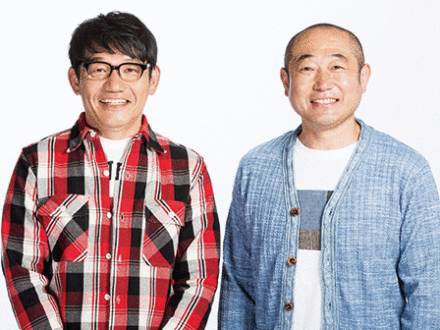訪問看護ステーションや高齢者ケア施設で生じやすい
人事労務に関するトラブルと対応策、
またトラブルの防止策について解説いただきます。
[Q&A]問題行動の多い有期契約スタッフ。
更新時に労働条件を引き下げてもいい?
中山 伸雄
なかやま のぶお
社会保険労務士法人Nice-One 代表 / 社会保険労務士
人手不足の昨今、正社員以外の非常勤スタッフを貴重な戦力として雇用している事業所は少なくないでしょう。事業所は、非常勤スタッフと1年や半年などの期間を定めて「有期労働契約」を結んでいるところが多いようです。
筆者は、事業者から「能力や勤務態度などに問題のある有期契約スタッフの労働条件を引き下げたいが問題はないか?」という相談をよく受けます。そこで今回は、有期契約スタッフに対して契約更新時に労働条件の引き下げ、さらに雇止めをしてもよいかといった相談事例を紹介します。