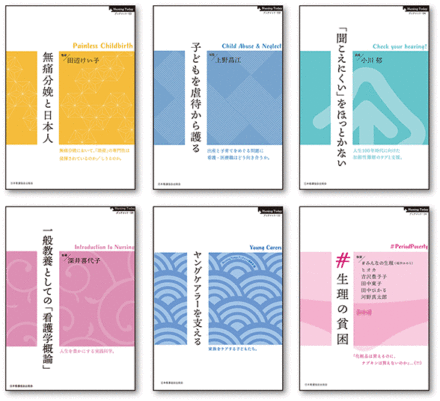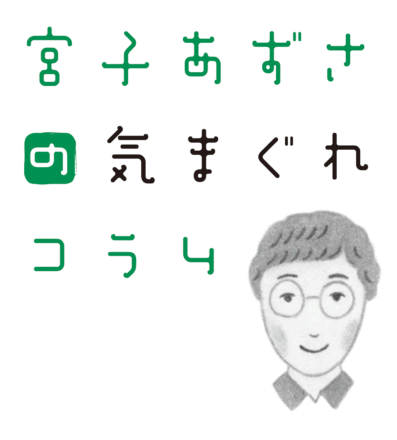佐藤美穂子 さん
(さとう・みほこ)
公益財団法人日本訪問看護財団
常務理事
1972年高知県立高知女子大学家政学部衛生看護学科卒業。同大学、東京白十字病院、日本看護協会、厚生省での勤務を経て、2001年より財団法人日本訪問看護振興財団(現・公益財団法人日本訪問看護財団)事務局次長。2002年より現職。
1993年の初版発行、1997年の新版へのリニューアルを経て、このたび第4版として改訂された本書。その監修・執筆者である日本訪問看護財団常務理事の佐藤美穂子さんに、改訂のねらいと主なポイント、さらにステーション管理者に求められる役割や訪問看護をめぐる今後の展望などについてうかがうとともに、ステーション開設にチャレンジする方々への応援メッセージをいただきました。