◎質問2 新人研修の担当者に求められる心構えとは?
[質問別の動画一覧]
[関連書籍]
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
◎質問2 新人研修の担当者に求められる心構えとは?
[質問別の動画一覧]
[関連書籍]
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
◎質問3 新人研修で最終的に目指すところは?
[質問別の動画一覧]
[関連書籍]
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
◎質問5 新人看護職員研修に対する今後の展望について
[質問別の動画一覧]
[関連書籍]
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
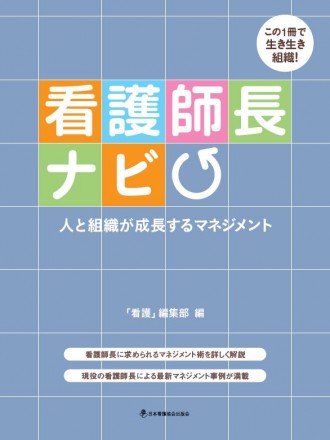 ◆この1冊で生き生き組織!
◆この1冊で生き生き組織!
◆看護師長に求められるマネジメント術を詳しく解説
◆現役の看護師長による最新マネジメント事例が満載
看護師一人ひとりの価値観は多様化し、ワーク・ライフ・バランスの推進と併せて、その働き方も複雑になっています。部署のリーダーとして、医療の高度化や患者のニーズに対応する一方で、スタッフ一人ひとりを支援し、病棟管理や労働改善に取り組む師長への期待は、さらに大きくなっていると言えます。
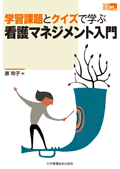
好評既刊『看護師長・主任のための成果のみえる病棟目標の立て方』の著者・原玲子先生の新刊が発行されました。『学習課題とクイズで学ぶ看護マネジメント入門』(目次はこちら)です! 初めて看護管理を学ぶ学生や復習したいナースの方におすすめです!
ここでは月刊「看護」2011年12月号「SPECIAL INTERVIEW」に掲載した原玲子先生へのインタビュー記事の全文をご紹介します。