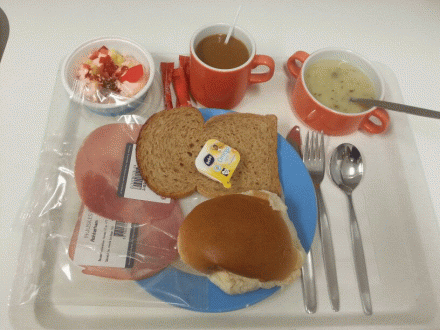文と写真:森 淑江
(INR日本版 2012年春号, p.111掲載)

ザンビアの首都から400㎞離れたカロモ郡のクリニックで活動する公衆衛生の隊員(右端)から話を聞く筆者(左端)。
1992年から2年間、中米のホンジュラスで看護教育に関する仕事をしたことをきっかけに、看護分野の国際協力に取り組み始めました。今では国際看護学の分野を確立すべく奮闘しています。
群馬大学で国際看護学の教育と研究を行いつつ、日本がODA(政府開発援助)として国際協力を行う際の実施機関、独立行政法人国際協力機構(JICA)青年海外協力隊事務局技術顧問(長い!)を務めています。
1965年に青年海外協力隊が創設されて以来、86の開発途上国に3万6,000人以上のボランティアが青年海外協力隊員として派遣されてきました。このうち2,438人が看護職(保健師・助産師・看護師)で、保健衛生部門の42%を占めており、2番目に多い養護隊員の558人を圧倒的に引き離す数です。

 158号に掲載したクリティーク記事を
158号に掲載したクリティーク記事を