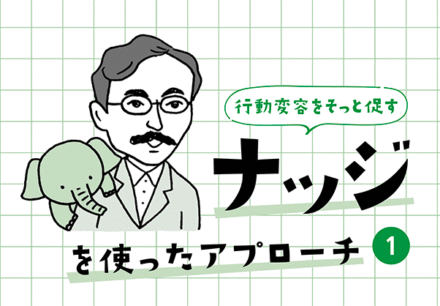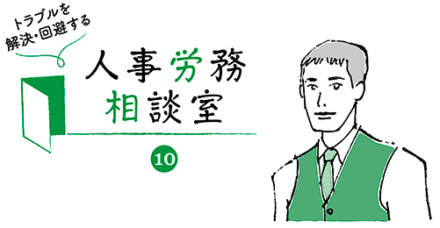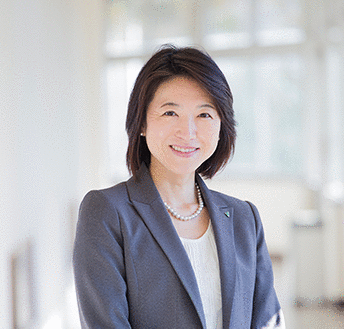ナッジとは、人の心理特性に沿って望ましい行動をしたくなるように促す設計のこと。この連載では、3人の医療職をめざす学生がナッジを学ぶ姿を通して、看護・介護に役立つヒントを示します。
頭でわかっているのに
行動できないのはなぜ?
竹林 正樹
たけばやし まさき
青森県立保健大学 博士/行動経済学研究者
相手を動かすということ
竹林 相手に望ましい行動をしてもらおうとしたけれどうまくいかなかった、という経験はありますか?
難波 私のまわりで、病気がひどくなるまで受診しない人がいて……。
竹林 最先端の治療方法が確立されても、患者が受診しないと医師は治療の提案すらできません。特に看護や介護では、心身の健康のために相手の行動変容を促したいと考える場面は多いでしょう。この連載では、「科学的根拠に基づいて人を動かす方法」を学んでいきます。人を動かす方法には、大きく分けて4つの段階があります1) 。
①正しい情報の提供(普及啓発)
②行動したくなる環境の整備(ナッジ)
③褒美と罰の設定(インセンティブ*1)
④選択の制限(強制)