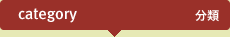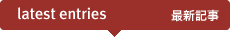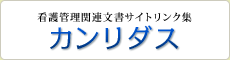文と写真・山中 郁
(INR日本版 2012年夏号, p.104に掲載)

山間で津波の難を逃れた普門寺を訪れると、県の天然記念物の百日紅が悠然と出迎えてくれました。
2012年3月11日。世界を震撼させた東日本を襲った大震災から、ちょうど1年が経ちました。私はこの日、宮城県気仙沼市総合体育館(通称“ケーウェーブ”)の合同慰霊祭に参加するため、気仙沼市にいました。
慰霊祭の代表者の方々の中に、震災当時高校2年生だった被災者の女性がいました。彼女は津波で7人の家族を失ったと話し、その一人ひとりに心のこもったお別れの言葉を読み上げたのですが、おじいさん、おばあさんに続いて、それぞれ中学生、小学生、就学前だった幼い妹たち、そしてお父さんへの手紙と続きました。
メッセージを聞きながら、家族7人の最後の一人が、そうであってほしくないと思いましたが、やはりお母さんへの言葉だとわかった時は、言葉がありませんでした。大家族でにぎやかな毎日を過ごしていたであろう普通の17歳の少女が、一晩で最も近い家族を全て失ってしまったのです。
私は心底、この少女がこの1年間、生きることを選択してくれてよかった……と思いました。
今回の震災で、建物の倒壊や火災などで亡くなったのは全体の5%ほどで、90%以上の方は地震後の大津波により命を落としました。建物などに閉じ込められた人の救出を想定していたであろう多くの緊急支援団体や自衛隊は、水没による被害を受けた被災地を前に、初日から多くの遺体の収容をすることになったそうです。
陸前高田市ならびに気仙沼市では、それぞれ2,000名近くの被害者が出ており、そのうち1,500名前後の方々のご遺体が各市の遺体収容施設に運び込まれ、身元確認作業が行われました。その時、看護師などの緊急支援者たちがとった行動の一つが、ご遺体の復旧作業でした。
病院でのエンゼルケア同様、ご遺体をきれいに清拭し、服を着せ、髪にくしを通し、化粧を施し、“欠けている部分”はタオルなどで補い、見た人のショックが少ないように配慮されたそうです。
2008年に大ヒットした映画『おくりびと』のように、日本人は概してご遺体に敬意を払う民族ではないかと思います。私がなぜ、今回の震災でこの点に注目したのかと言うと、そこに英国とかなりの違いがあると気づいたからです。
ロンドンの小児病院のPICUで勤務していた時は、週に3〜4人の子どもたちが亡くなることもありました。危篤状態にあれば家族総出で集まり、亡くなる時には「お願いだから諦めないで、先生!」と両親が懇願し、誰かが大声を張り上げて泣き叫べば、他の人が「もう楽になったんだから……」と宥める。その光景は変わりませんが、状況を受け入れた後が、驚くほど違うのです。
日本では、多くの家族(特に子どもの両親)がご遺体を家に連れて帰りますし、「寂しいだろうから……」と、常に誰かがそばについていることが多々ありました。ある18カ月の娘を亡くしたご両親は、小さな身体をタオルに包んで腕に抱き、車で自宅に帰られました。
一方で、私が知る限り英国では、病院で子どもが亡くなった後、ご遺体を病棟か病院に預け、家族全員引き上げてしまうことがほとんどでした。亡くなったホスピスに葬儀まで預かってもらうこともありました。
おそらく日本人には、心臓が止まっても、身体はまだその人の一部だという考えがあるのではないでしょうか。だからこそ今回の震災の後も、一体一体のご遺体にケアを施し、棺に納め、お花を飾り、必死の身元確認作業が行われていたのではないか、と。
日本は臓器移植例が他の先進国よりも極端に少なく、臓器移植のドナーも少ないですが、それはこのような、“心身一体”の精神も無関係ではないのではと思います。ロンドンで勤務していた頃、交通事故で脳死状態となった14歳の娘の臓器提供を、数日の短い期間で選択してくださったご家族がおられました。
魂と身体が完全に別物と考える彼らは、脳死の説明を受け、魂はすでに身体から離れてしまったと考えることで、この難しい決断ができたのかもしれません。
この4月から、以前とは別の国際協力NPO、特定非営利活動団体HANDSで、再び東北震災復興事業や、アフリカのケニア共和国で行われている国際保健事業に携わることになりました。
生まれ育った国や環境が違うと死生観にも大きな違いが生じます。ケニアプロジェクトでは開発途上国の現地の人々をサポートし、プロジェクトを達成さる必要がありますが、英国と日本のそれぞれ性格の異なる医療現場で働いてきた経験をそこでどう生かしていくかが、今の私の課題です。
やまなか・かおる
神奈川県出身。国内の病院(小児科)に勤務後、2000年に渡英。現地病院の小児科及び小児病院などに勤務。震災を機に帰国し岩手県で震災復興事業に携わった後、今年の4月からNPO法人HANDSのプログラム・オフィサーとして活躍中。