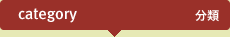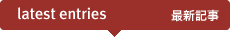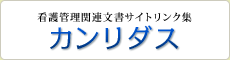文と写真:杉江美子
(INR日本版 2012年夏号, p.103に掲載)

トロントのシンボルの一つ「CNタワー」の高さは553.33メートルで、世界で5番目に高い自立式建築物。
昨年3月の東日本大震災は筆舌に尽くしがたい出来事で、遠くカナダに住んでいてもニュースとともに矢継ぎ早に入ってくる映像は非常に強烈でした。
カナダの多くの友人・知人、職場の同僚が私に、日本の家族・親戚・知り合いは大丈夫か、日本は大丈夫か、何か手伝えることはないかと、幾度となく尋ねてくれました。時には知らない人まで、私が日本人であるとわかると、お悔やみと励ましの言葉をかけてくれました。私を通して日本に向けた言葉だと思います。
遠くからニュースや第三者を通じて知り得たことなど取るに足らないのでしょうが、それでも私は改めて「日本人」であることを痛感し、この出来事を通じて日本の「地域耐性」(Community Resilience)と「助け合い」の精神に驚嘆しました。
日本にいれば当たり前のことが、海外からは非常に新鮮に映り、私は単に日本人であるというだけで、そのことを誇らしく思いました。
かなり以前、日本人はボランティア精神があまりないと自己批判していたのを覚えています。しかし「ボランティア」というカタカナでは表せない、また「奉仕」という意味だけではない、「助けて助けられる」「助けて教えてもらう」という日本の「助け合い」は、カタカナ英語が入ってくる以前から確実に存在していたと私は信じています。
「ボランティア元年」と言われた17年前の阪神・淡路大震災よりずっと以前からあったはずです。でなければ震災後の自然発生的な草の根の「助け合い」は生まれなかったでしょう。それは、日本人がもともと持っていた「助け合い」の精神を再確認した年だったと私は思います。
東日本大震災における日本の「地域耐性」は、日本の精神文化のなせる業だというのが海外の多くの人の見解です。しかしそれだけでしょうか。もしそれが日本特有のものなら、他の国々はそれを学び取り入れることができません。何が日本の「地域耐性」をつくり出しているのでしょう。
それは「助け合い」に密着したものだと思うのです。この精神そのものは日本特有のものではありません。社会的動物である人間すべてが共有するものです。つまり「助け合い」を根底とした「地域耐性」は世界中で可能なはずです。私は今、現在の日本の「助け合い」と「地域耐性」の間にあるものが知りたくて、それをカナダで伝えたくて仕方がありません。
カナダのトロント市保健局で働いて10年半になり、勤続年数が自己最高となりました。働きながら通った公衆衛生学修士課程をこの6月に卒業です。数年前から、修士課程を終えたら1年間の休暇を取り、国際協力の現場に戻ろうと計画していました。しかし震災のニュースを最初に見た時に、この休暇は東北へ行こうと決めました。
日本看護協会のe-ナースセンターを通じて東北3県の被災地での保健師募集に応募し、宮城県看護協会eナースセンターが柔軟に対応してくださったおかげで、市の委託事業である仮設住宅の訪問活動の仕事をいただきました。この7月から10カ月間の予定です。常に日本へ帰りたい帰巣本能と放浪癖、そして加齢による安定志向が交錯した結果なのかもしれませんが、長い間の私の願望は、こんな形で実現しようとしています。
昔、青年海外協力隊に行く時、ある友人から「日本にもいっぱい困っている人がいるのに、なぜわざわざ海外の人を助けに行くのか」と質問されました。バブル経済崩壊前のことです。若かった私は、当時の先進国と開発途上国の格差の背景にある複雑な構図など知らなかったし、それが協力隊参加の理由でもなかったので、ただ「私がしたいことなのだ」としか答えられませんでした。
初めての国際協力経験に、肩肘張って背負いきれないほど膨らませた使命を抱えて臨みましたが、実際には援助に行って援助していただいたのは自分でした。
もし今、その友達から同じ質問を受けたとしても結局「私がしたいことだから」としか答えられないでしょう。でもこの夏の東北行きには、過去3回の国際協力の機会を私に与えてくれた日本に対する恩返しの思いが含まれています。質問した友達に、27年後の今度こそ、日本の困っている人を助けに行きますと報告したいのですが、やめておいたほうがよさそうです。
来年の今頃は、きっと恩返しどころか、もっと恩をもらっているような気がするからです。
すぎえ・よしこ
大阪府出身。1984年より青年海外協力隊の保健師としてマレーシアへ、1989年からはJVC/SHAREの看護師として、カンボジアで国際援助に携わる。1996年よりトロント市在住。