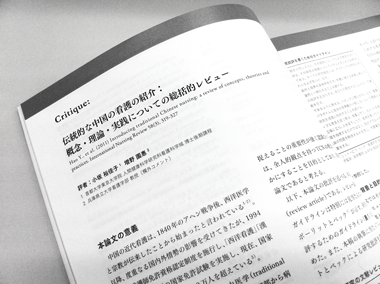
INR日本版155号(4月1日発売)に掲載された翻訳&クリティーク記事より、評者・増野園惠先生ご執筆の「Advice」部分を、以下にご紹介します。
伝統的な中国の看護の紹介:概念・理論・実践についての総括的レビュー〈Hao Y., et al. (2011) Introducing traditional Chinese nursing: a review of concepts, theories and practices. International Nursing Review 58(3), 319-327〉
評者:小坂裕佳子・増野園惠
Advice:
今回の論文クリティークは、筆者と若手研究者らとで行う論文抄読会の第1回目で取り上げられ検討されたものである。この抄読会のメンバーは、看護システムマネジメントに関心を持っており、この分野の研究動向や研究手法への理解を深めることを目的に集まっている。
しかし、メンバーの多くが基礎看護学、成人看護学、高齢者看護学、在宅看護学などの領域で看護基礎教育に携わっており、検討する論文のテーマは実際には非常に多岐にわたる。したがって、今のところテーマや研究デザインにはあまりこだわらず、見識を広められるよう、また互いに学びあう(メンバー同士、またクリティークを通して論文の著者から学ぶ)姿勢で取り組んでいる。
今回の論文も、この抄読会がターゲットとするテーマから少し外れた感はあったものの、伝統中医看護(TCN)の紹介ということで、タイトルと要約からは非常に興味を惹く論文に思われた。小坂も述べているように、全人的なアプローチや代替補完療法に対する関心が高まる中、どの看護実践分野においても実践に新たな視点を与えてくれるのではないかと期待があったからである。


 「インターナショナル ナーシング レビュー」日本版155号(2012年春号)より連載コラム「海外でくらす、はたらく。」をスタートしました。
「インターナショナル ナーシング レビュー」日本版155号(2012年春号)より連載コラム「海外でくらす、はたらく。」をスタートしました。







