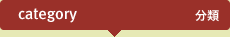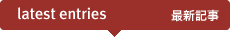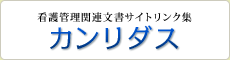地域包括ケアシステムの先進事例として、全国から注目されている「幸手モデル」。地域住民とともにこのモデルをつくった筆者の医師としての歩みを振り返り、幸手モデルの本質に迫ります。 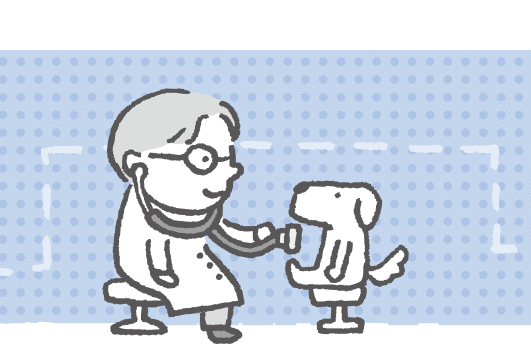
➑社会人人生で初めてケアをされた経験
忘れかけていた
自身を信じて動くことの大切さ
2012年、埼玉利根保健医療圏地域医療連携推進協議会が設立され、いよいよ、われわれが知る限り全国初の二次保健医療圏単位における地域医療連携システム「とねっと」(Electronic Health Record:EHR)の構築に向けた検討が始まりました。利根保健医療圏すべての医師会・基幹病院・保健所・7市2町の行政機関に参加してもらうことに成功したのです(2018年度からは、歯科医師会や薬剤師会も参加)。
とはいえ、協議会設立後しばらくは、思うように進まない議事にいら立ちを感じました。協議会の構成員からは「数値目標を立てるのはよくない」だとか、「長期的な運用など考えずに、かかりつけ医カードを市民に配って事業を早期に終わらせろ」「なぜ参加しないといけないのか」等、厳しい意見もありました。この状況に困り果てて泣きついた平井愛山先生*1からは叱咤激励と助言をもらいましたが、私には平井先生のような県立病院長と同じ振る舞いができるはずなどありません。ほかにも多くの人たちから励ましやアドバイスを得ましたが、閉塞した状況は変わりませんでした。
ところが、一度他者からのアドバイスをシャットアウトし自身の感性や判断を信じて行動しようと思ったころから、不思議と状況が好転し始めました。どんなに経験や洞察力のある偉大な実践家であっても、現場で試行錯誤する当人の状況を正確に理解することは困難です。余談ですが、平井先生は常に携帯電話を持ち歩き、病院職員や患者、研修医からの連絡に24時間対応していました。講演の最中であっても、ちゅうちょせずに電話に出ることは仲間内でも有名な逸話で、私自身、そこまでの覚悟は持てないとかねてから感じていました。
何かうまい方法はないかと画策する一方で、自身の抱えた状況を打破するためには、自身の感性を信じて協議会の構成員1人ひとりと向き合い、胸襟を開いて徹底して対話を重ねるしかないことを忘れかけていたのです。
→続きは本誌で(コミュニティケア2021年10月号)