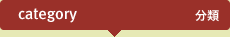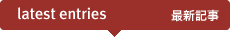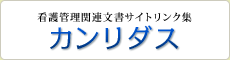認知症をもつ人がたどる経過や生活の変化に応じた専門職の役割・動きを捉えるため、本書の著者らは数回にわたる多職種カンファレンスを実施しました。それぞれが「点」でかかわるケアを俯瞰的に眺めたとき、看護職にはどんな課題が浮き彫りになるのでしょうか。
認知症をもつ人がたどる経過や生活の変化に応じた専門職の役割・動きを捉えるため、本書の著者らは数回にわたる多職種カンファレンスを実施しました。それぞれが「点」でかかわるケアを俯瞰的に眺めたとき、看護職にはどんな課題が浮き彫りになるのでしょうか。
■認知症とは何か?
「認知症」という言葉は、臨床でどのように使われているでしょう。「認知症にはなりたくないよ」「認知症があるみたいで、困ったなあ」といったように、まずポジティブに話されることはありません。それどころか「あの人、ニンチ入ってるから結構大変よ……」などと、もはや正確な言葉さえ使われず、話す人同士で“何となくのイメージ”が共有されるものにすらなっていませんか?
そもそも「ニンチ(認知)が入っている」なんて日本語としておかしいですし、認知機能が低下した状態に対してそんな言葉を用いることなど、医療職として到底承服できません。このような言葉への扱いからも想像できるように、認知症の「理解」はさらにひどいものです。「認知症って、知っていますか?」という質問にはほとんどの人がYESと答えるでしょう。しかし「では説明してください」と聞かれたら、医療職でさえほとんどの人が下を向いてしまいます。いったい、「認知症」とは何でしょうか。
認知症は診断名ではありません。実行機能障害などの認知機能が低下する一連の症状をまとめた呼称であり、認知症にはそれら症状の原因となる疾患名が存在します。アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性疾患、脳血管性認知症、正常圧水頭症……、その数は実に100種類以上にも及びます。疾患名が異なれば、当然ながらそれぞれの対応も一緒でよいわけがありません。しかも、神経変性が基盤にある進行性の疾患(アルツハイマー型認知症など)の場合は症状も時々で変わるため、その都度、個別性を重視したアプローチを再考する必要が生じます。
■認知症はいつ、誰が、どう支えるのか?
こうした症状の進行を的確に把握し対処していくために、いつ、誰が、どのようにサポートすればよいのでしょうか。病院で働く看護師は、目の前の患者さんが退院後にどうなるのかを知りません。今この状態で退院して大丈夫だろうか。家で生活していくためにできることはないだろうか。現在行っているケアを次に担う他の専門職にどう伝えればいいのだろうか……。個々の患者さんの立場になってみれば、シームレスなケアが重要なことは言うまでもありません。しかし、それがうまくできていない現状が多々見受けられるのです。
今年の4月に、京都で第32回国際アルツハイマー病協会国際会議が開催され、世界中から認知症ケアの関係者が集まりました。その中には認知症をもちながら生活する当事者の方々もおられ、会議の目玉企画として彼らによるワークショップがありました。そこでは「参加者それぞれの地域ごとにいるはずの当事者たちの思い、生活上の困難などをよく理解し、安心して一緒に暮らせるまちづくりを考えてほしい」という意見がありました。
住みやすいまちづくりは、個々に暮らす人々の生活をよりよくすることの積み重ねによってつくられます。そこで私たちに必要なのは、生活というものを改めて見直すことです。人間の生活は高度な認知機能が複雑に組み合わさって成り立っています。進行性の認知症疾患ではそれらが損なわれ、徐々に生活が難しくなるのです。
■看護職に何ができるのか?
認知症の当事者は、国際会議で自分の意見を発表できる人だけではなく、すでに言葉を失っている人もいます。こうした方々の生活も、本人がどうしたいのかをよくよく知った上で「できること」を中心にサポートする必要があります。そこで重要なのが早期発見と早期対応であり、これは政府の掲げる認知症施策(新オレンジプラン)の中でも最重要課題です。しかし今はむしろ「早期発見、早期絶望」といった構図が出来上がっています。認知症と診断されてしまったがために、これまでの生活が一変してしまった人も少なくありません。診断はいったい何のためにあるのでしょうか?
私たち看護職はもう一度、診断された人へのかかわり方を見直さなければなりません。患者さんの生活に診断名による不具合が生じないように、できるだけ支援することが重要です。その過程で疾患が治癒すればよいのですが、治癒せず慢性の経過をたどり、しかも進行性の疾患の場合はどうすればよいでしょうか。認知症疾患の診断を受けた人は自立支援から始まり、介護保険の適用、リハビリ名目のデイサービス通い、症状が進行するとグループホーム、そして特別養護老人ホーム……といった制度やサービスに収まる形で生活することになっています。いずれも対象者が楽しくよりよく生活できるように、それぞれの場でスタッフや専門家が工夫を重ねています。しかし、知らず知らずのうちにそうして用意された枠に、その人の人生を当てはめていないでしょうか。たとえば、「しばらくは在宅で生活できるけど、いずれは家で看ていくのが無理になるから、そのときは施設かな」……といった見方をしてないでしょうか。認知症という診断がついたら、みんな「認知症」のように生きなければいけないのでしょうか。
私たち看護職はいつでも、その人の生活を支える存在です。どのように暮らしたいのか、対象となる人々の生活において何が重要なのかを常に考え続けることを専門としています。ぎりぎりまで粘ってみて、それでもその生活を諦めなければならないとき、決断は認知症をもつ本人が下さなければなりません。疾患はあくまで、そこにあった生活の中に後から入り込んでくるものです。その影響を最小限に止めることが「寄り添う」ことだと思います。そこで重要なのは本人や家族の生活基盤を固めることです。そしてその実現は看護職だけでは不可能であり、多職種連携によって進めていかなければなりません。
認知症のケアは放っておいても進展しません。いろいろな人が絡み、それぞれの専門性が発揮されてこそ、認知症をもつ人や周囲の人を優しく包みながら、彼らの生活基盤を固めることができます。本書ではそうした思いをたくさんの当事者や専門職種が共有し協力し合って出来上がりました。ぜひ、日々の実践に活用してもらえたらと思います。
山川みやえ
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻准教授/
公益財団法人浅香山病院臨床研修特任部長

本書掲載の「疾患別典型10事例〜時系列チャート」の詳細は、
(PCでご覧ください)。
山川みやえ・繁信和恵 編著
●A4判変型 184ページ
●定価(本体2,160円+税)
ISBN:978-4-8180-2040-5
日本看護協会出版会
(TEL:0436-23-3271)
-「看護」2017年8月号「SPECIAL BOOK GUIDE」より –