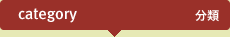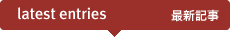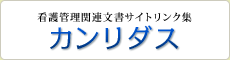評者:坂本 すが(さかもと すが)
評者:坂本 すが(さかもと すが)
日本看護協会会長
著者である都倉亮氏は、事業家として活動していた55歳の夏、ステージ4の中咽頭がんを告げられる。その告知場面の記述に始まる本書には、放射線と化学療法の壮絶な闘病生活、直後の再手術、そして2年後の本書執筆中に発見されたがん転移との対峙が、氏の人生を織り交ぜて綴られている。
闘病記を読む度に思うことであるが、本書からも、病を生きるという患者の体験と人生に看護職はどう向き合うのかを、改めて問われた思いがしている。がんを病むということは、がんとその治療による心身の苦痛から免れない体験であるばかりか、家族や大切な人びととのつながり、昨日まであった日常、さらに明日を生きようとする希望を脅かされる体験である。その人の人生と切り離せない体験であるからこそ一層、臓器を見て人を見ない現在の医療の実態が浮かび上がって胸に迫る。
私たち看護職は病む人の最もそばにいる者として、おそらく常に患者さんの心身の苦しみを知ることに最大限努めている。しかし、私たちがどんなに知ることに努めようとも、病を生きるという体験とその人生は知り尽くせないことを、本書を読んで私は素直に認めざるをえない。
私たちが看護の標準的ケアの知識と技術をしっかりとベースに持って、病む人に何をしなければいけないか判断し、手を差し伸べても、その手はまだ患者さんに遠く届いていないか、あるいは差し伸べた方向がずれていることがどれほど多くあることだろう。では、そうした限界を抱える私たちにできることは何であろうか。知ろうとするだけでは足りない。
知り尽くせないことはわかった上で、見えないものを見、聞こえないものをも聞こうとして、自ら患者さんのほうへ歩み寄り、なお近づこうとすることより他にないのではないか。そうやって初めて「その人」という個人が、看護職である「私」の目と心に見えてくるのであり、そこからやっとケアと呼べるものになる。
「けっして自分では体験したことのない他人の感情のただなかに身を投じる」ことを求めたナイチンゲールの言葉は、おそらくそのことを言おうとしているのであり、ケアに従事する者の病む人に対する誠実さと、看護という職を生きる自身の人生への誠実さの必要を言っているのだと私には感じられる。この2つのものへの誠実さがない限り、患者という「その人」はいつまでも見えることはなく、ただルーティンの業務に流されて終わってしまう。
故澤瀉久敬氏が看護について語った言葉を私は今一度思い返す。看護職とは、病の影に死を予感しておののく人のそばで、その人の伴侶として生きる職業なのだ、と。それは、よほど重い覚悟がいる。しかし、氏はさらに、死におののく人の伴侶として生きることが、誰よりも素晴らしい人生を生きていることなのだというのである。
もうこれ以上は乗り越えられないと、ふと挫けそうになった時には、看護という職を自ら選んだことを思い出してほしい。たしかに私も素晴らしい人生を送らせてもらっているのだ。それは、ひとえに患者さんによってである。この書を読んで私は看護職を選んだ自分を改めて考えさせられた。
-「看護」2013年3月号「Special Book Review」より –