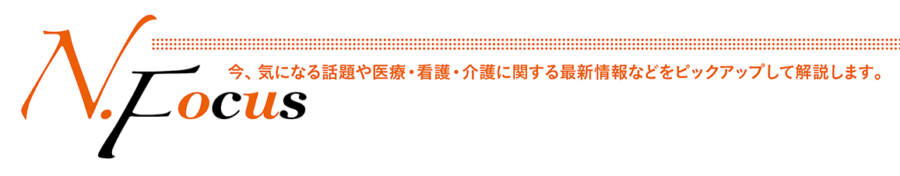病院の看護師と地域の資源がつながることの成果
福井 トシ子 ● ふくい としこ★1
国際医療福祉大学大学院 副大学院長
公益社団法人日本看護協会 前会長
平野 一美 ● ひらの かずみ★2
医療法人弘遠会すずかけヘルスケアホスピタル 看護部長
★1 福井トシ子。2017年から日本看護協会会長を3期6年務め、2023年6月より現職。2024年4月に日本で3校目となるDNPコースを開講する。経営情報学修士、保健医療学博士。
★2 平野一美。2012年に磐田市立総合病院の副院長兼看護部長、2017年に藤枝市立総合病院の副院長兼看護部長に着任。2021年4月から現職。認定看護管理者。
地域の看護管理者との連携の重要性は誰もが理解しているものの、実際にはうまくいかないケースが少なくありません。本稿では、平野一美さんが実践した「磐田市・森町の病院・訪問看護ステーションの看護代表者がつながる会」ならびに「藤の花かんかんネット」の事例から、施設を超えた看看連携の実現のヒントを紐解きます。
はじめに
福井トシ子
地域包括ケアシステムの推進、新たな財政支援制度(地域医療介護総合確保基金)の創設などにより、医療政策の分野でも地方分権の推進が進められています。2018(平成30)年度からは「地域医療構想」を反映した医療計画、介護保険事業(支援)計画の運用が始まり、また、地域包括ケアシステムの実働部分となる介護保険地域支援事業「在宅医療・介護連携推進事業」が全市町村で完全実施となりました。このように、地域における医療・介護提供体制の構築が推進されており、市町村、保険者、医療機関など、多様な場の看護機能の連携強化がいっそう求められています。
地域包括ケアシステムが推進される中、看護の実践の場は地域の多様な場にさらに広がっています。これまで看護の3職能、保健医療の各専門職種それぞれにより、特定の対象、特定の場所などに対して行われてきた取り組みや活動を、地域としてとりまとめ、連携・連動したものとすることで、人々の生活に寄り添った、より合理的で利便性の高いものとすることも必要とされています。
看護ケアの対象者は、従来の枠組みを超えて多様化しており、これらに伴い、看護提供の場も広がっています。人々が健やかに生まれ育ち、疾病や障害があっても地域において生活を続けるための地域包括ケアシステムの構築・推進は、地域共生社会実現の基盤です。この中で、医療と生活の両方の視点を持つ看護職には、重要な役割があり、「あらゆる場、あらゆる人に対する良質な看護の提供」が求められています。