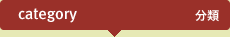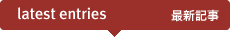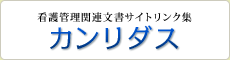「人生の終焉を迎える人」(自分で死を意識するようになった時期から亡くなるまでの期間に生きる患者・利用者)にナースはどのような声かけをすればよいのか……
さまざまな現場から報告します。
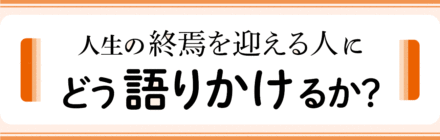
終焉を迎える患者さんたちに向けて語れなかった自分
生駒 あづさ
公立富岡総合病院 3B病棟 副主任
●コメント●
内田 陽子
群馬大学大学院保健学研究科 教授
連載2回目となる「人生の終焉を迎える人にどう語りかけるか?」では、地域の中核病院で臨床一筋20年になる生駒さんからの報告です。うまく語りかけることのできなかった過去の事例における生駒さんの想いと、それをもとに語りをするためのヒントを内田陽子さんがコメントします。
私の勤める公立富岡総合病院は群馬県の西部に位置し、日本でも有数の高齢化率の高い南牧村や上野村を医療圏に抱える地域中核病院です。同時に富岡甘楽医療圏で唯一の急性期医療を担う総合病院でもあります。HCU、緩和ケア病棟をはじめ内科系・外科系および産婦人科の病棟を持ち、24時間体制の救急診療にも対応しています。地域がん診療連携拠点病院でもあり、COVID-19に罹患した患者さんも積極的に受け入れています。
父の看取りと看護師への志
私は10歳のときに父を悪性リンパ腫で亡くしました。今から35年ほど前の話になります。当時は「がん告知」もされず、疼痛コントロールも発展途上の段階でした。当初は父の見舞いに通っていましたが、苦しそうな父の姿を見て、途中から足を運ばなくなりました。
入院して3カ月後、父は冷たくなって自宅に帰って来ました。父の病気を教えてもらえなかったこと、父の病気が治らなかったこと、父が苦しみながら死んでいったこと、そしてなによりその現実から自分が逃げたことを誰かに責任転嫁をしたかったのか、私は医療従事者を恨んでいました。
しかし、高校時代に「ホスピス」という言葉に興味を持ち、各地にあるホスピスや在宅の緩和医療に関する医師や看護師の本を読んで、看護師をめざすことにしました。その後、看護師免許を取得して父の主治医がいた病院・病棟を配属先として希望して就職しました。今、その病院で臨床一筋の看護師として現在に至ります。本稿では、私が出会った人生の終焉を迎える患者さんたちとの語りを振り返ります。