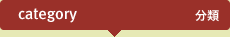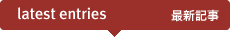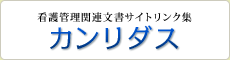〈コミュニティケア探訪・No.32〉
【深刻な病状や余命を患者さんとどう話し合うか? 英国の老舗ホスピス・緩和ケアの知恵——デービス・カニングさん】
■文と写真・村上 紀美子(医療ジャーナリスト)
本連載を基に『納得の老後 日欧在宅ケア探訪』(岩波新書)を刊行。ドイツ・オランダ・デンマーク・イギリス・日本の柔軟なケアの姿から、5年後、10年後の“納得のケア”を探りました。
❍
深刻な病状や余命などの厳しい事実(バッドニュース)について本人と話し合うのは難しく、緊張するものです。そうしたコミュニケーションに関して、英国のホスピスや緩和ケアの豊かな知恵を取材しました。医師・看護師・介護職にとって、患者・家族との会話の参考となるでしょう。
❍
厳しくつらい事実を話し合うトレーニングが必要
病状や治療効果が思わしくない、人生の終わりが迫っているといった厳しい事実(バッドニュース)は、誰にとっても話しづらいものです。どこで、どのように死を迎えたいか、最後の1週間の医療はどうするか、などを話し合うタイミングは見極めにくく、話すこと自体への恐れもあります。医師や看護師にとっても常に難しく、「苦手だ」と感じるのも当然でしょう。
そこで、患者とのコミュニケーションのスキルを磨き、バッドニュースを話し合う訓練をすることが重要になるのです。
英国政府と国民医療サービス(National Health Service:NHS)は、2008年ごろから、エンドオブライフケア・ストラテジー(終末期ケア戦略)を進め、病院・施設・地域にも、ホスピスのような看取りケアやコミュニケーションを普及する政策をとっています*。
その一環で看取りに携わるすべての人―ボランティア・ケア助手・病院看護師・地域看護師・家庭医など―へ、患者さんのつらい症状を緩和するケアや、患者とのコミュニケーションのトレーニングなどが順次行われてきました。その教育担当のお1人、セント・ジョゼフ・ホスピスの教育部門のリーダー(当時)であるデービス・カニングさんに聞きました(写真1〜2)。
バッドニュースに関するコミュニケーションの原則
カニングさんは「バッドニュースをめぐるコミュニケーションには原則がある」と言います。そのポイントを教えていただきましょう。
●患者さんを支える人となるべく一緒に
話し合うときは、患者さん1人でなく、患者さんの支えになる家族や友人に、なるべく一緒にいてもらいます。患者さんがショックで説明を理解できなかったとしても、その人たちが覚えていれば、後で確かめることができますから。
●敬意を持って、落ち着いて、静かな声で
相手に敬意を持って、穏やかな低めの声で発音は明瞭に。患者さんが落ち着きを保てるように、「私がこの患者さんだったらどう感じるか」と考えながらゆっくり話します。
…………………………………………………………………………………………………………
■セント・ジョゼフ・ホスピス
約110年前、アイルランドから来た5人の修道女が結核患者のために創立した英国初のホスピス。1960年前後には、シシリー・ソンダースがここで疼痛緩和のプロンプトン・カクテルの研究を行った。
2013年現在、病床は51床(リハビリテーション・レスパイトを含む)。在宅ケアの患者は200〜300人で、スタッフは3チーム合計12人。デイホスピスや介護家族支援、夜間のホスピス電話対応なども充実している。病院・家庭医・地域保健センターなどが参加する地域の看取りケアネットワークのけん引役。
■デービス・カニングさん/Deebs Canning
(前・セント・ジョゼフ・ホスピス 教育リーダー)
オーストラリアで看護を学び、ホスピス・急性期病院で緩和ケアスペシャリストナース・訪問看護などの経験を経て、英国に移住。その後、セント・ジョゼフ・ホスピスの教育リーダーと同時に、シティ大学講師を務める。2011年、ウエスト・ロンドン大学講師に就任。
→続きは本誌で(コミュニティケア2014年9月号)