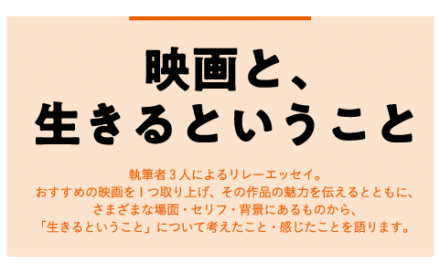(No.21)
名画が語る“普遍性”
『火垂るの墓』
岩田 健太郎
神戸大学大学院医学研究科 教授/神戸大学医学部附属病院感染症内科 診療科長
感染症内科医。『ワクチンを学び直す』『抗HIV/エイズ薬の考え方、使い方、そして飲み方ver.3』など著書多数。趣味は、映画や落語の鑑賞、スポーツ観戦など。
映画史上に残る傑作
8月15日、終戦の日に「金曜ロードショー」★1で放映していたのを録画して鑑賞。今回で2回目だ。最初に観たのは1988年で、島根県の映画館。『となりのトトロ』(以下:『トトロ』)と同時上映だった。昔の映画は2本立てが基本で、案外、昭和の日本人は暇だったのだろう。
その後、『トトロ』はDVDも買って子どもと何度も何度も観た。しかし、『火垂るの墓』はそれっきり何十年も観ていなかった。率直に申し上げて、初見時の印象は悪かった。「なんでこんな気持ち悪くて、暗い映画をつくったの?」というのが高校生だった僕の感想で、ハッピーエンドの『トトロ』に水を差すようなバッドエンドの映画は不快ですらあった。当時の僕は、映画と言えばアニメかハリウッドか香港のカンフー映画くらいで、政治にも歴史にも興味がなく、日本の実写映画はクソダサい、アメリカが一番カッコいいと決めつけ、シルベスター・スタローンがベトナムとかアフガニスタンでマシンガンをぶっぱなすような映画が大好きだった。まあ、今で言うところの「ネトウヨ」。勘違いしている人が多いが、ネトウヨは「右翼」と言っているわりには日本の文化にも歴史(ファクト)にもまったく興味がない。かつての自分がそうだったので、とてもよくわかる。穴があったら入りたい。
そんなわけで、第一印象は最悪だった本作だが、2025年の今、観返すと映画史上に残る傑作であった。これだから、第一印象は案外当てにならない。小説も、漫画も、映画も初見時ににわかに判断、判定しないほうがよい理由がここにある。映画のレビューサイトなどの「星」評価など少しも当てにならぬ。
★1 日本テレビ系列で毎週金曜日に放送されている映画番組
『火垂るの墓』
1988年/日本/88分
監督 高畑勲
原作 野坂昭如
配給 東宝
制作 スタジオジブリ
原作は、神戸の大空襲を体験した野坂昭如氏による直木賞受賞作。父が出征中に空襲で母を亡くした14歳の少年・清太が、4歳の妹・節子とともに“生きよう”とした姿をリアルに描き出していく。罪のない子どもや病気の母たちを容赦なく炎に飲み込んでいく空襲。周囲の人々に頼ることができない幼い清太と、優しさを見せる余裕のない大人たち。戦争の愚かさと哀しさを、高畑勲監督が渾身の力で描いた、いのちの物語。