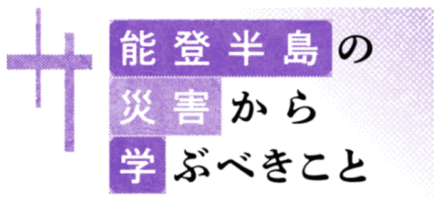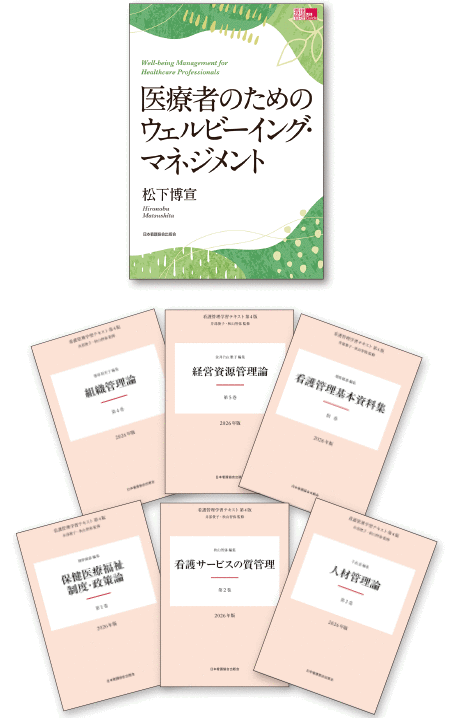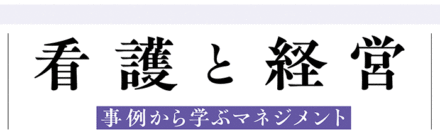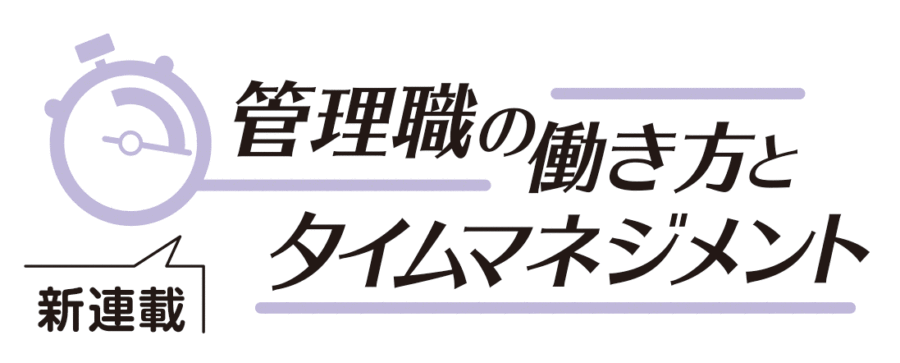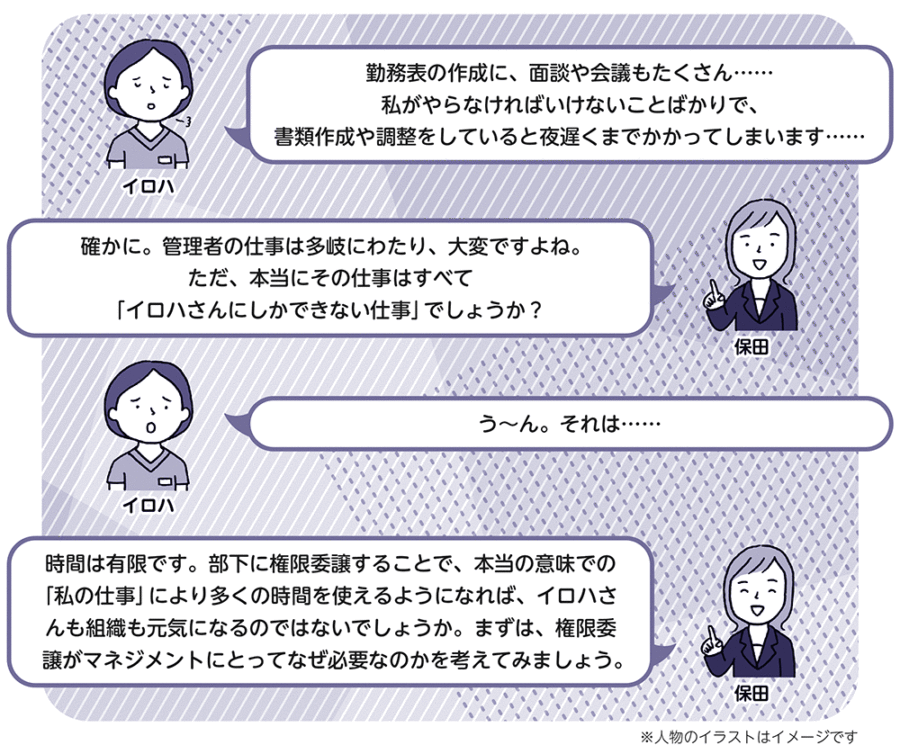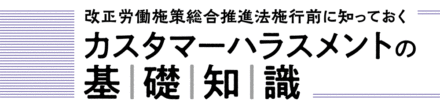第9回
「先取り適応」で災害復興に備える
災害を契機とした地域の再構築
加藤 孝明
東京大学生産技術研究所 教授・社会科学
研究所 特任教授
◉1967年愛知県生まれ。東京大学工学部市工学科卒業、同大学院工学系研究科修士課程修了。博士(工学)。
同大学工学部附属総合試験所助手、同大学大学院工学系研究科
都市工学専攻助手、助教、同大学生産技術研究所准教授を経て
現職。災害シミュレーション技術・まちづくり支援技術の開発を
行うほか、「防災【も】まちづくり」を提唱し、総合的な地域づく
りの新しいモデルを実践的に模索する。都市計画学会計画設計賞
(2022)他、受賞多数。
はじめに
本稿では、まず復興の6法則を提示し、復興の普遍的特性を述べた上で、災害復興の方針の多様性に触れます。続いて、復興できない状況 を避けるために不可欠な復興の事前準備について述べ、地域の将来像を描く「先取り適応型復興」を具体例とともに論じます。
復興の6法則
世界および日本の復興事例をレビューすると、共通する以下の6つの法則的特徴が浮かび上がります。これらの法則は今後の災害復興にも当てはまると考えられます。