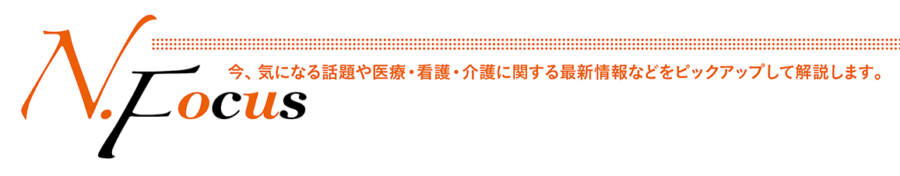災害時における情報管理の手法「クロノロジー」
東京都多摩府中保健所における
災害時保健活動の充実に向けたクロノロジー研修から
石田 千絵●いしだ ちえ
日本赤十字看護大学 看護学部地域看護学 教授
佐藤 茜●さとう あかね
東京都多摩府中保健所市町村連携課 市町村連携担当 課長代理
佐藤 太地●さとう たいち
日本赤十字看護大学 看護学部地域看護学 講師
河西 あかね●かさい あかね
東京都多摩府中保健所 地域保健推進担当課長(保健所統括保健師)
自治体保健師は、大規模地震災害やパンデミック等の健康危機発生時に、被災地自治体において、また、被災地自治体への保健師等支援チームの一員として活躍しているところですが、自治体保健師が平時にどのような役割を担っているのか、有事に向けてどのような演習をしているのかあまり知られていません。そこで本稿では、東京都多摩府中保健所が管内の市町村向けに実施した、災害初期に重要となる情報管理の手法「クロノロジー」研修について紹介します。
はじめに
石田 千絵
近年、災害の大規模化、頻発化が進む中で、災害時における円滑かつ迅速な対応についての社会的要請が高まっています。わが国の災害対策法制は、「災害対策基本法(1961年)」を中心に災害サイクルごとに必要な体制が整えられ、応急期の救助に対応する主要な法律は「災害救助法」によります。
災害救助法は、1946年の南海地震を契機に、1947年に制定されたのち、その後に発生した大規模自然災害によって明らかとなっていった各々の教訓を基に改正を重ねて、現在も災害初期の重要な法律として位置づけられています。
災害救助法が適用されない場合、救助の主体は市町村ですが、適用されると、被災都道府県(保健所)が、応急救助の直接的な実施(日本赤十字社による救護班の派遣委託も含む)をします。そして、国と被災した都道府県(保健所)と市町村が連絡・調整をしながら、被災状況の情報を集約し、応援職員の派遣や他の都道府県や市町村からの応援要請をすることで、あらゆる応急救助を直接的・間接的に行い、被災住民の安心安全や健康の保持に寄与できるようになっています1)。つまり、「連絡・調整」「情報の集約」といった「情報」が発災時の応急対応に重要なリソースとなるのです。
→続きは本誌で(看護2025年12月号)