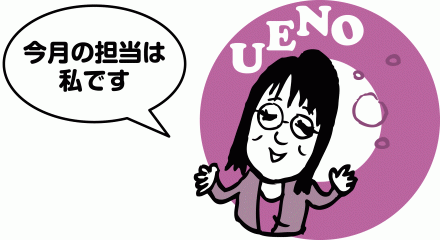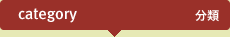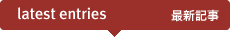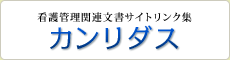福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。
“寄り添う”ことの難しさ
文:上野まり
今日、2人に1人はがんに罹患するといわれています。私のまわりにもがん罹患者が増えました。検診の普及により早期に発見・治療され、5年、10年と長期にわたって生活の中に医療を取り込みつつ生きる人も多くなり、「がんは慢性疾患」と認識される時代になったと感じます。しかし先日、1人の友人が急に逝ってしまいました。
妻とのメール
その友人の妻から、ある日突然、「夫ががんに罹患した」とメールがありました。驚いてすぐに病院に行こうとしましたが、後のメールに「彼は誰にも会いたくない、知らせたくないと言っている。看護師のあなたにだけこっそり知らせたの」と書かれていました。
その後も彼女とのメールのやりとりは続きました。お互い仕事をしているため、通勤時間や寝る前にメールを送り合いました。「がん=死」をイメージし、急いで駆けつけたり、電話したりするしか方法がなかった時代に比べ、いつでもどこでも連絡できる便利な時代になったと思います。
彼らはできる限りの治療を施して治したいと考えており、私もその思いに強く共感しました。治療を進める中で、彼の症状の変化にもうだめなのか、まだ大丈夫なのかと一喜一憂する彼女の様子がメールからうかがえました。時には、彼の不機嫌な言動に傷ついたり自分を責めたりと、普段は冷静な彼女らしくないメールも届きました。
仕事と看病と主婦業……大きな負担に潰されそうな彼女に、私はどう返信すればよいか悩むこともありました。メールは便利である半面、一度送信したら修正できず、後にも残ります。彼女から届いた短いメールの意味をどう捉えたらよいのか、この内容のメールを受け取ったら彼女はどう感じるだろうと、看護師だからこそ軽い発言にも重みが加わってしまうようで、返信にはいつも時間がかかってしまいました。
家族と医療職の気持ちのギャップ
副作用のつらさの一方で彼の病状は好転しませんでした。「こんなにつらいなら死んだほうがまし」と、あらゆる治療法を駆使しても治したいと言っていた彼の気持ちも揺らぎ始めました。そして主治医からインフォームド・コンセントがなされ、治療を中止。「限られた時間を有意義に過ごすように」と、医師や看護師、誰もが彼らに言いましたが、「そうは言われても……」と彼女は動揺を隠しきれないようでした。
その後、彼女からメールで、緩和ケアに切り替え在宅療養すること、また訪問診療・訪問看護・訪問介護などについて「よくわからない」と相談されました。介護保険の上限を超えてしまうと悩んでいたので、私は、訪問看護は医療保険でも利用できることを伝えました。希望する地域の訪問診療や訪問看護は即座に利用できるものではない現実も知りました。